[ad#ad-1]

歳を重ねるにつれて音楽の趣味も変わっていくのは当然のことなのかもしれない。
小・中学生、テレビを見る家庭で育ったのであればやはりJポップから音楽を聴くようになるのかもしれない。
今はYouTubeでいくらでも自分の知らない音楽を聴くことはできるけれど、今まで自分が聴いたことのない音楽を聴くというのは難しいことだ。
まずはじめにその音楽を聴くにはきっかけのようなものが必要になってくるからだ。
時々テレビで演歌や民謡を歌う小さな女の子とか出てくるけど、あれだってその子が自発的にコアな音楽に目覚めたわけではないだろう。演歌を好む家庭環境に育ったり、近くに歌の先生がいたりしたはずだ。それをきっかけに彼女も歌い手になったのだと思う。
高校生くらいになると、音楽の幅はぐっと広がるような気がする。大学へと進むとフェスなんかにいくようになるだろう。付き合う人間の種類も変わってくる。大学を卒業して社会人となれば音楽の趣味は継続されるか、もしくは深まっていくんだろう。僕は後者だね。
もちろん中には「おれ、音楽ってあんまし聴かないんだよね!」っていう人もいるだろう。
別に多くのジャンルの音楽を知っているからといって、それがえらいとかそういうわけじゃない。
えっと、今日は何が書きたいかというと、
自分が新しく聴き出した音楽のはなし。

今ちょこちょこ聴くようになったのは
“Ambient(アンビエント)”
というジャンルの音楽だ。
コトバンクによると
「環境音楽。 作曲家や演奏者の意図を主張したり、聴くことを強制したりせず、その場に漂う空気のように存在し、それを耳にした人の気持ちを開放的にすることを目的にしている。 シンプルで静かなメロディーを繰り返す場合が多く、画廊のようなスペースでビデオアートと組み合わせて用いられることもある」
らしい。
「ほわんほわわわ〜〜〜ん..」
って感じでちょっとスピリチュアルな感じがするのだ。
このジャンルを知るようになったきっかけは、好きなアーティストがラジオで「最近アンビエント聴くんスよね」と言っていたことと、仲間が酒を飲みながらアンビエント・ミュージックをiPhoneでかけていたからだ。「何それ?いいね〜〜!」ってなったから。
今はYouTubeで誰かの作った1時間から3時間くらいのリミックスの音楽を流しているだけで、特定のアーティストが好きなわけじゃない。いや、知りたいんだけどね。どんな人がいるんだろうね?
そういば、山梨県の甲府にあるキャンプ場でアンビエント・ミュージック専門の野外イベントもあるみたいだ。
10月1日開催みたい。
アンビエントは意外に作業をしている時にはあまりマッチしない。
ただ、僕が聴いていて「いいな♪」と思う瞬間は、アンビエントを聴きながら酒を飲んでいる時だ。
まさしく「チルアウト〜〜〜..」って感じ(笑)
温泉につかりながら聴いてもいいんじゃないかなって思う。
僕にとってのアンビエントとは「酒に合う音楽」なのかもしれない。
仲間と酒を飲んでいると時々こういう自分の知らない音楽が入ってくる時がある。
たぶん、もっと年齢が若かったころに出会ったのであればあまりピンとこなかったであろう音楽も、歳をとるとだんだんとその良さに気がついてくるものなのだ。すこしずつお酒が飲めるようになる感覚と少し似ている気がする。最初っから酒飲めるヤツもいるけどね。
こういうジャンルの音楽は「マイナー」に分類されてしまうのだろうか?
テレビやラジオで大々的に扱われる音楽が「メジャー」ということになるのだろうか?
それを区別するひとつは、そのジャンルの音楽が商業的かであったり、より多くの人の共感を得るかどうかに依るのだろう。
いや、自分の聴く音楽のジャンルを掘り下げていくという意味においてはそんな区別なんて関係ないのだ。
そこになんらかのきっかけがあればいい。
クラシックとか聴いてみたいけど、なかなか敷居が高い。作曲者とかよくわからねえけど、知ってたら頭よさげな気がする(笑)
まぁ、好きな音楽を聴こうぜってこと。
ゆる〜〜く、ね♪
[ad#as-1]
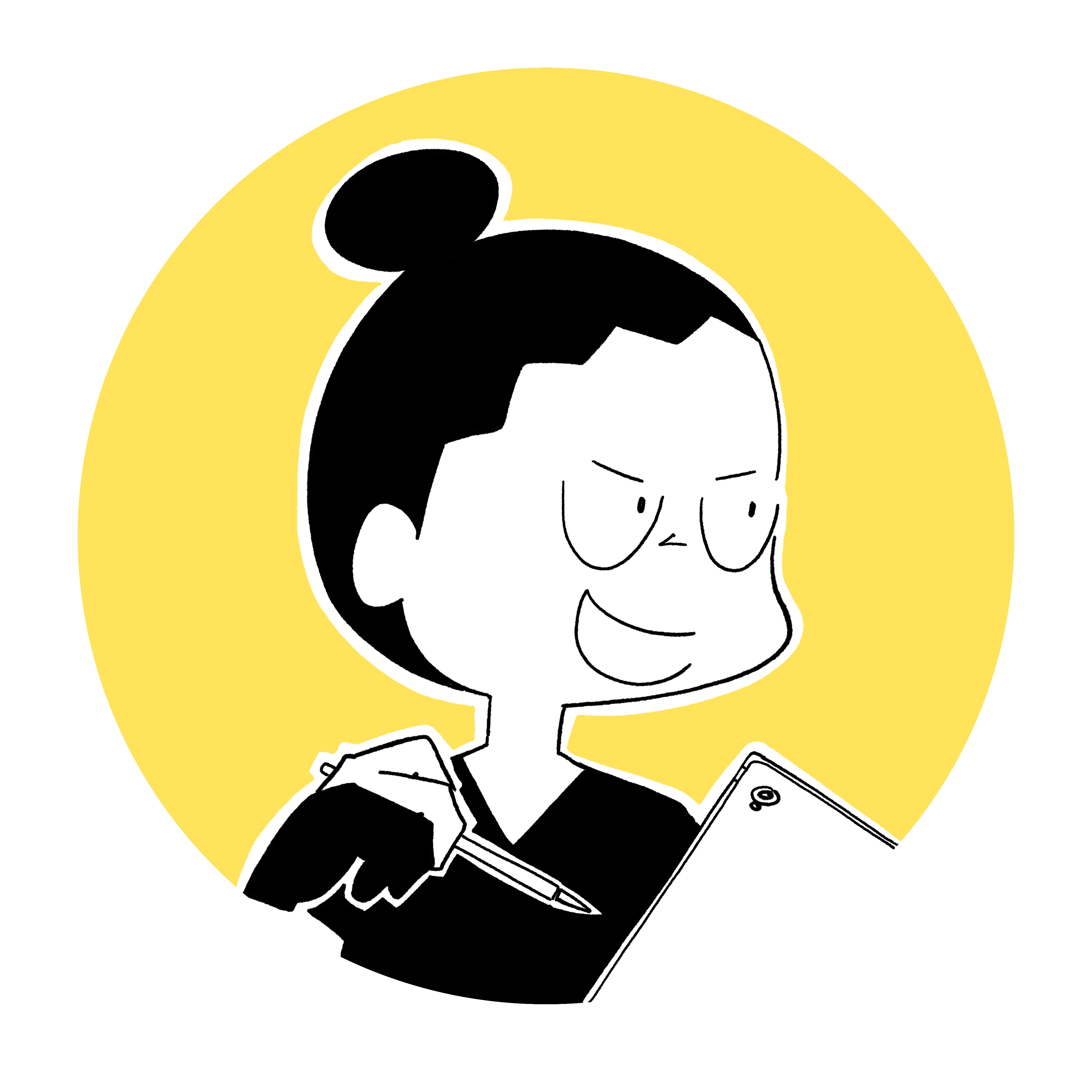
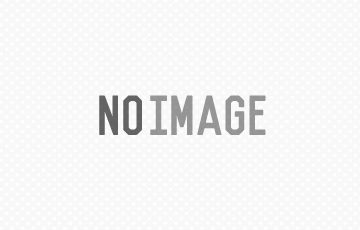


コメントを残す