[ad#ad-1]
ジョン・アーヴィングの小説を僕が初めて読んだのは大学生のときだったと思う。
当時から僕は村上春樹を読みあさっていて、彼の作品全てを読破する勢いでブックオフに足しげく通っていた僕は、長編から短編、さらにはエッセイ集へと次々に読んでいった。
それだけでは飽き足りず彼の翻訳した書籍まで手を伸ばすようになり、そこでたまたま読むことになったのはジョン・アーヴィングの「熊を放つ」という小説だった。
それから、僕は世界一周の旅に出て、中国でアーヴィングの本を見つけた。
こう書くとなんだかミステリアスな感じがするけど全然そんなことはない。たまたま泊まったゲストハウスにペーパーバックが置いてあっただけだ。「ホテル・ニューハンプシャー」というタイトルだった。
誰も読んでなさそうなその本を僕は「本の交換」と称して、自分の読み切った本一冊(沢木耕太郎の「深夜特急3」だったと思う)と交換して、旅をしながらちょこちょこと読み進めていった。英語で書かれていたので読むスピードは相当遅く(っていうか読まない期間が長かかった)
やっと読み終わったのはそれから7ヶ月くらい経ってからのことだった。
そして、最近僕はジョン・アーヴィングの作品をもう一昨読み終えた。
今朝方読み終えたばかりだ。
「ガープの世界」
というのが本のタイトルだ。

町田のブックオフに行った時になんと100円で売られているのを見つけたのだ。100円だぜ?いや、消費税込みで108円だけどさ、上下巻セットで216円って衝撃の安さだよね。もう誰も読まないのかもしれないな。
そもそも、僕はこのタイトルから気になっていた。
だって「ガープ」だもの。
「ガープ」って聞くと僕はONE PIECEに出てくるルフィのおじいちゃんを思い出す。
まぁ、漫画家なんてさ、キャラクターのネーミングをする際に参考にした作品なんてほとんど読まない場合が多いみたいだ。
『あ!この名前使えそう!もらいっ!』ってな具合でキャラクターの名前をつける場合が多いから、漫画と小説はほとんど接点なんてないけどさ、それでもタイトルがかっこよすぎたよね。なんてたって「ガープ“の世界”」なんだもの。言葉の響きからも惹かれるものがあった。
最初この本を手に取った時、僕は最後まで読み切れるか自信が持てなかった。
もし退屈な小説だったら途中で飽きちゃうんじゃないかと不安になったのだ。
長編小説のは最初の50ページくらいが小説の世界に浸れるかどうかの分かれ目だと思う。
僕が「ガープの世界」を読み始めたその日はちょうど恵比寿に用事があった。新百合ケ丘から新宿へ向かう電車の中で黙々とこの本を読んでいた。
僕は待ち合わせとなるとだいぶ早く到着して心理的に相手の優位に立とうとするよくわからない癖があるんだけど、なんと30分も前に到着して、おまけに待っていたヤツが30分も遅刻してきたもんだから(シンペイ兄さん!あなたですよ!)僕はたっぷり本を読むことができた。
まとまった読書の時間が取れるとあとはスラスラと読み進めることができる。
それからは毎朝起きて一時間くらいは読書の時間をとっていた。
読めば読むほど僕は「ガープの世界」の世界へと引きずりこまれていった。
読後は映画を見た以上の疲労感を覚えた。
小説の奥行きは半端なく広かったから。
まず設定からして異色だった。
タイトルは「ガープの世界」となっているが、ストーリーはガープが生まれる前から始まる。
ガープ誕生秘話みたいなことが最初の数十ページを使って延々と書かれているのだ。この最初の部分が、読者がガープの世界に入っていけるかどうかの分かれ道だと僕は思っている。
主人公ガープの母親のジェニー・フィールズがかなりの変人だ。考え方が偏っていて頑固でクソがつくほど真面目なのだが、どこか行き過ぎている。ジェニーがガープの父親と出会うくだりなんて、読んでいてちょっと気分が悪くなるようなシーンの連発だ。不思議とそのシーンがばっちし頭の中に映像として残る。それくらいインパクトがあった。小説家の上手いってこういうことをいうんだろうな。
ガープが誕生したあともストーリーはしばらく母親や、彼らが暮らすスティアリング学園の話ばかりで、『一体いつになったら主人公が出てくるんだ?』ともどかしい気持ちになってくる。
作者のジョン・アーヴィングはいくつか同じテーマを他の作品でも扱っており、ホテル・ニューハンプシャー同様、この物語も家族の話だった。だからこそ主人公をこと細かく説明したのだろう。
僕が一番興味を持ったのは、主人公のガープの職業が小説家だったことだ。
ジョン・アーヴィングという作家が自分と同じ職業の人間を作中に登場させ、さらには作中作までも作ってしまうのだ。さらにさらに、小説の世界の中で作中作の批評なんかも書くもんだから、読んでいるとよくわからなくなってくる。
それでもガープの生き方をたどっていくと、ところどころに作者が自己を投影しているような箇所がいくつも出てくることに気づく。『もしかしたらこれは作者自身のことなんじゃないか?』とガープと作者(アーヴィング)を重ね合て読み進めると面白い。
だが、作中でガープは「小説の中に自己を投影することはクソだ」みたいなことを書いているから、これもよくわからない。読者を混乱させるのも小説の上手いポイントなのかもしれない。照れ隠し的な?
小説は主人公ガープの人生を一貫してたどっていくのだが、彼を取り巻くシーンやシチュエーションがめまぐるしく変わるので読んでいて飽きることはない。
ガープが高校卒業と同時にオーストリアへ母親と渡ったり、一作目の小説を書こうともがく姿があり、アメリカへ戻り結婚したあとはライターズブッロクに陥りなかなか次の小説が書けなくなるという情けない姿を晒すこともある。毎日ランニングは欠かさず、専業主夫として料理と子育てに励むことなど、生活臭がかなりリアルに感じられる描写がたくさんある。
単純に読んでいて面白かった。
映画化もされているんですね。ロビン・ウィリアムズかぁ。
また「熊を放つ」や「ホテル・ニューハンプシャー」とも共通することがこの小説の中でも見つかった。
まず、熊が出てくるということはおなじみだ。どうして熊なのかわからない。それでも同じようなテーマが他の小説でも見つかると、なんだか別の街で知り合いにばったり出くわしたような気分になる。
彼の扱うテーマのひとつに「旅」もある。舞台はアメリカのこともあれば、オーストリアに主人公たちが移動することもある(実際に作者はウィーンで暮らしたこともあるみたいだ)。
そして、小説に出てくる人物たちは、偏屈だったり、真面目すぎたり、ユーモラスだったりするのだけれど、誰も彼も結局は幸せになれない虚しさみたいなものは共通しているような気がした。
小説の中に、作家がこの世界の真実を描こうとする姿が描かれている。
世界の有り様は人によって様々で、一概に「これ!」と言えるような世界像はない。
だが、いつの時代でも変わることのない人間の本質はあるのかもしれない。人が生き物である以上、いつかは死に絶える存在だ。
それは悲しいことでもあるし、避けることはできない。
僕は彼の小説を読むと、そういう虚しさを感じるのだ。
僕は文学的な批評やそのような視点で小説を読み解くことは得意出はない。ほとんどできないって言ってもいいくらいだ。
小説を読みきって、最後の「解説」を読んだり、時にはネットで書評を調べたりして『ふむふむ。なるほどな。この小説はこういうことを言いたかったんだな』って考えるくらいだ。
ストーリーラインだったら説明できるけど、書評となるとちょっとできないな。これを書いてて『読書感想文ってやっぱり書くの難しいな』って思ったくらいだもん。
書評も書く練習しないと上手くならないのかもね。
書評じゃないけど、「街角のクリエイティブ」の田中泰延さんの映画評とか面白いよね。あれも、映画を語る知識があるからあそこまで面白く書けるんだろうなって思います。
えっと、、、
僕は何を書きたいんだっけな?
「ガープの世界」を読み終わって、その読書感想文みたいなことを書きたいなって思ったんだけど、なかなかビシっと決まらないものですね。
よし!次回頑張ろう!
[ad#ad-1]
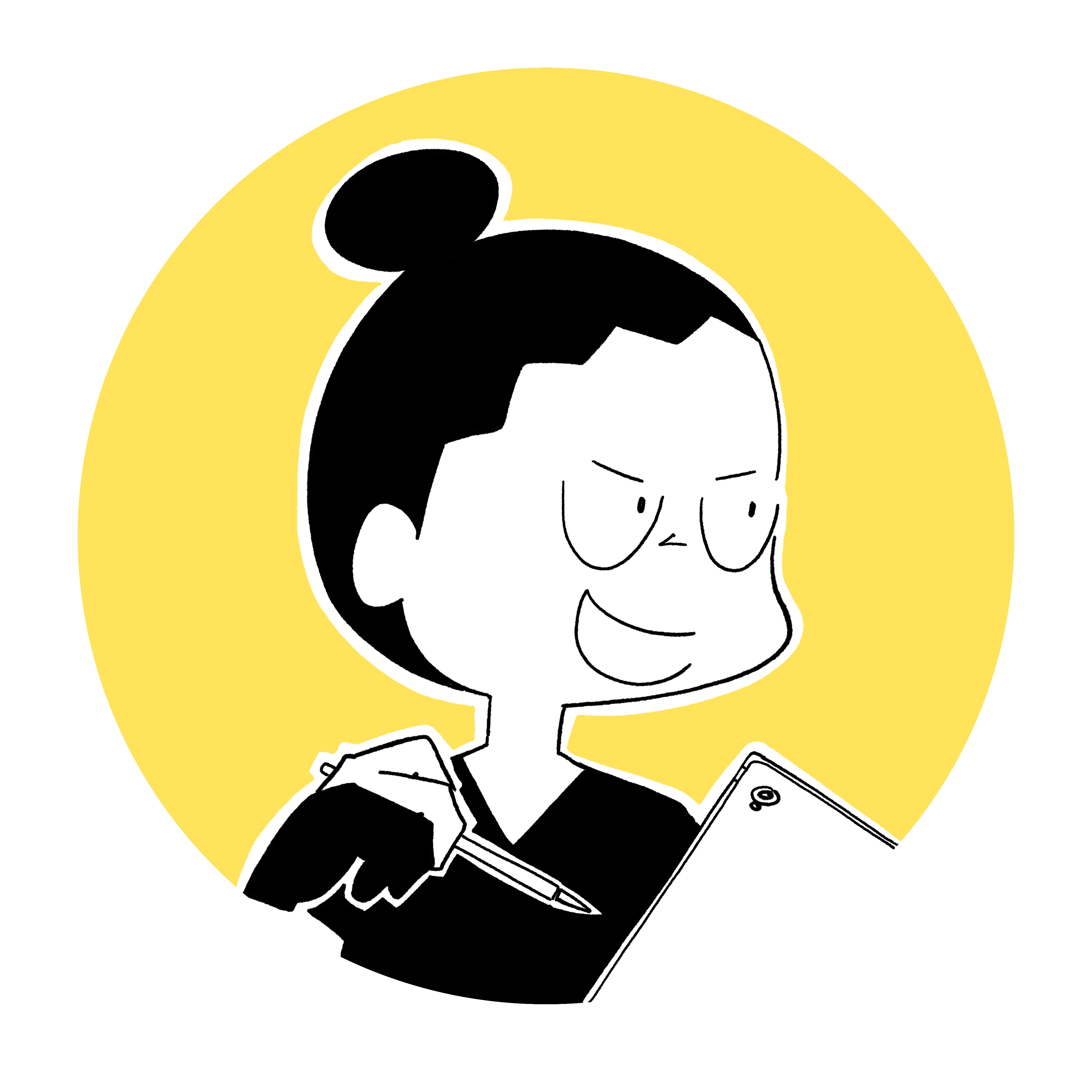



コメントを残す