[ad#ad-1]
「あぁ、そんなにも僕のことが好きだったなんて知らなかったよ」
そう答えると、彼女は怪訝な顔をした。「いったいこのバカは何を勘違いしているのだろう?」と言いたがっていることは火を見るよりも明らかだった。
教室はダルマストーブのせいでもってりと暖かく、その上に置かれたヤカンからは湯気がくゆっていた。坊主頭の男子生徒がカップ麺にヤカンのお湯を注ぎ込こむと満ち足りた表情を浮かべた。何人かの生徒たちは黒板から最も遠い、オセロでいうと戦略的な要になりそうなポジション(つまり教室の角、窓際)でファッション雑誌を回し読みしていた。
いつもの風景。いつもの昼休み。僕の半径1.5メートルを除けば。
窓を閉め切っているせいで窓ガラスは白く曇っており、外の景色を見ることはできない。見るものと言っても、そこから見えるものと言えば葉の抜け落ちた木々と寒々しい山肌しかないのだけれど。
その時僕は地元の高校に通う2年生だった。
都会でも田舎でもない関東に住み、両親は共働きで、兄弟はいない。小・中学校ではそれほど勉強に励んだわけでもないが、かといって他人から「バカなヤツ」と見下されたくないという、十代の少年にありがちなエゴを持っていたせいもあり、僕は地元で一番成績のいい高校へと進学することに決めた。
中学まではよかった。ちょっと勉強すれば、すぐにクラスの優等生になれたからだ。
だが、高校へ進学するとそれは違った。なんせ同じような「クラスの優等生」たちが寄せ集まってその高校を進学校たらしめていたからだ。
最初の中間試験を受けた時点で、僕は自分がどの程度に位置する人間なのかを理解した。ただ、その現実を受け入れるまでには少し時間が必要だった。次の試験までにいくらか勉強を頑張ったが、成績も順位も上がらなかった。
その時点で僕は自分の能力の限界を悟った。
『あぁ、僕なんてこんなものだったのか』
そう受け入れてしまえば、学校生活にしまりがなくなっていくのは当然の流れだった。落葉樹が冬になると葉を落とすくらいに自然なことだった。
冬になるとイチョウの木から大量の葉が落ち地面を埋た。そんなイチョウ並木を学校前を歩くとローファーの裏には悪臭を放つ銀杏がこびりついた。
自然の摂理に沿った僕の下降線を描く学園生活。
まぁ、人生なんてこんなものなのかもしれない。余計な希望を抱かない分だけ、生きやすい。将来の夢だとか希望だとかそういう青臭いものにうつつを抜かす心配もないだろう。だって叶わない夢や希望を描いたところで、かえって失望が大きくなるだけだもの。それなら惰性で生きた方がまだ気が楽だ。
僕はニヒリストでペッシミストで、それでいて学校においては無価値な人間だった。いったいなんで周りの人間たちはこの退屈極まりない学園生活を楽しむことができるのだろうかと僕は不思議で仕方なかった。
休み時間になると僕は机の中からiPodを取り出してイヤホンを耳に突っ込み、何も音楽をかけずに机に突っ伏していた。
それが僕の休み時間の過ごし方だった。
何人かの人間はもうしわけ程度に僕に話しかけてきた。
彼らは僕という人間に興味を抱いていたわけではないということはすぐにわかった。
彼らは「独りになること」を恐れていたのだ。そう周囲から見なされることを嫌い、徒党を組むことによって安心したいだけの人間の集まりだった。
僕はそうじゃない。そんな馴れ合いに煩わされるよりかは自ら孤独を選ぶ。周囲の嘲笑は気にしない。どうとでも僕のことを言えばいい。どうせこの生活も永遠に続くわけではないのだ。
僕が彼らとした交流と言えば、ノートやCDなどを貸しあったりしただけだった。僕は音源を入れたUSBを彼らに渡すことはあったが、自分から何かを借りたという経験は一度もなかった。
僕はずっと孤独だった。
冬になると、
なぜだか心がざわついた。
何もないその場所を風が通過すると
虚ろな音が鳴っているような気がした。
「もしかして僕は宇宙人なんじゃないか?」
拷問的に退屈な学園生活をなんとか一年間乗り切って、さらに半年たったある日のこと。僕はそう思うようになっていった。
それまで観た映画の本数の累計は600本に及んでいた。一日2本映画を観ることは普通で、時には1.5倍速で4、5本の映画を観ることもあった。ほぼ休まず365日、毎日映画を見ていた。
映画館で上映しているものを観にいくこともあれば、レンタルショップでDVDを借りて来ることもあった。ありとあらゆるジャンルの映画を観た。年代を問わず手当たりしだい漁った。どんなに興味のなさそうな映画も辛抱強く最後まで観ることを自分に課していた。たとえゴダールの映画が高校生にとっては難解で退屈だったとしても僕は寝落ちすることはなかった。映像は僕の眼球を通過して情報として脳で処理され、そして僕の血や骨になっていくと本気でそう信じていた。
われながらよくやったと思う。
学校生活の方は徹底的に無生産のスタンスを貫いていたが、学校の外では間違いなく自分のためになった(であろう)活動をしていた。
映画を観ること。それだけが唯一の僕の救いだった。
好みはフルカラーになる前の白黒の映画だった。
チャップリンの喜劇やヘップバーンの恋愛映画が僕のお気に入りだった。CGが当たり前の現代映画とは逆光した半世紀以上昔の古ぼけた映画は、僕を空想の世界へと運んでくれた。
白と黒の画面にはなぜか温かみを感じた。出てくる俳優や女優のいささかオーバーな演技に人間味を感じずにはいられなかった。僕は生まれてくる時代を間違えたのかもしれない。
いや、僕は当時、実際にその場所にいたのかもしれない。
彼や彼女たちと同じように笑い合っていたのかもしれない。きっとどこかに時空的なひずみが生じて、何かのひょうしで意識だけがこっちの世界に飛ばされてーーー..
いけない。いけない。
これは最近観た映画の設定だった。
大丈夫。ちゃんと幼い時の記憶もある。
ある日突然、僕は同じように映画を見ている人間が集まりそうな場所を探すようになった。
今まで溜め込んだものを一気に放出したかった。純粋に誰かと映画について語りたかったのだ。映画を通して得て心の底に沈殿した何かを共有し、満ち足りた気分を分かち合いたかったのだ。
今となって急に友達が欲しくなったわけじゃない。ただ、僕は自分の抱えている想いを誰かと共有できれば、それでよかった。
それに二年生の秋となれば学内のヒエラルキーは一ミリの隙間もなくガチガチに固まっていた。程度の差こそあれ校内にはいくつかのコミュニティがあり、今の時期もうどこも欠員募集していなかった。たとえ無理矢理どこかのコミュニティに入ったとしても不協和音しか生まれないだろうことは分かりきったことだった。
そもそも僕はそういう凝り固まった人間関係を心の底から憎んでいた。
それでも念のため映画好きの学生が集うようなコミュニティを探してはみたものの、この学校には「映画研究部」なる部活は創立以来存在していないことがわかった。
まぁ、そんなコミュニティがあったところで、人との馴れ合いを嫌う僕は自ら距離を置いたことだろう。
誰かと映画の話をしたくて、僕は新しい映画を観るだけでは飽き足りず、映画に関する知識も深めようと、映画に関わる書籍も読み漁るようになった。
そのころには「アイツはどうも映画監督を目指しているらしい」という噂が広まっていた。そしていつの間にか「アートティスト=変人」というステレオ対応な僕専用のポジションが用意されていた。
「人とコミュニケーションをとるのが苦手なのはアートを志す人間には特有のことだ」とまで言われていたみたいだ。
僕としては全くそんなふうに自分を思っていなかった。
周りの人間が知らないだけで僕は饒舌だったし、弁が立った。喋らなかったのはそうしたいと思わなかったからだ。これは決して強がりなんかじゃない。近所のおばさんたちの間では「この町で一番落語家に近い青年」ともてはやされていたのだ。
そう。
僕は(すごく)年上の女性たちから人気を博していたのだ。
断っておきたいのだが、僕は映画を観ている人間であれば誰でもよかったわけではない。「あぁ、あの映画、よかったよね!」なんていう小学校低学年の児童でも言えそうな貧相な感想しか言えない人間とは口を聞きたくなかっただけだ。その時点でコミュニケーションブレイクが発生していた。
映画を心の底から愛し、自分の言葉で自分の観た作品の感想を述べられる、そんな感受性の豊かな人間を僕は探していた。
そう。僕は「誰か」を探していたのだ。
その「誰か」は間違いなく、この学校に、そして自分の身近にいるだろうということを僕は確信していてた。
視線を感じるのだ。
それは慣れきった嘲笑や奇異の目ではなく、明らかにそれまで感じたどの視線とも異なっていた。
どこか親密で暖かなぬくもりを感じる視線だった。
きっと向こうも僕とコンタクトをとるチャンスをうかがっているにちがいない。
僕は目立たないようにその視線の行方を探した。
なんせこっちは二年半も孤独を貫いていた身だ。境遇で言えば自主的に幽閉された塔の上のラプンツェルに他ならなかった。伸びきった髪の毛は、今ではオールバックにして頭の後ろでまとめ、ポニーテールにして垂らしている。ただし体格は親父譲りなので、正面から見ればスティーブン・セガールのようになっていた。だがあいにく母親譲りのその顔がナイーヴで神経質な僕の性格を如実に表していた。
そんな僕がいきなり行動を起こせば校内で僕の築いたポジションはたちまち居心地の悪いものに変わってしまうだろう。せっかく僕に暖かい視線を送ってくれた「誰か」にも迷惑が及ぶにちがいない。そうなったら向こうからコンタクトをとってくる可能性の芽は周囲のデリカシーのない干渉のせいで摘み取られてしまだろう。それだけは絶対に避けなければならない!
いったいどうしたら..
どうしたら
彼女を探し出すことができるのだろう?
きっと彼女はこの階のどこかにいる。
僕の本能はそう告げていた。
僕の高校の全クラスはA棟とB棟のふたつの校舎に分かれており、二年生はA棟の4階に3クラス、B棟に4クラスというふうに分かれていた。
彼女は間違いなく僕のいるA棟にいるはずだ。
もしかしたら彼女はクラスメイトなのかもしれないし、もしくは両側のどちらかのクラスにいるのかもしれない。
向こうからやってくるのはその視線のみだ。
あからさまに振り返ることはできない。僕はそんな品のない男ではない。かと言って視線に気がつかないほど鈍くもない。
どうする?
それはどこかの惑星からやってくる微弱な電波をキャッチしているようなものだった。
「アナタハドコニイルノ?
ハヤクワタシヲミツケテ」
そう考えると、僕は心を乱さずにはいられなかった。
向こうからやってくる電波を受信する装置はもっているのだ。それは僕の心だ。それなのにこちらからコンタクトをとることはできていない。
僕が今からやらなければならないこと。それは
こちらから電波を送る「発信装置」を作ることに他ならない。
僕は頭を悩ませてその方法を考えた。
制服になんらかのサインをつける?
だめだ。周囲にバレてしまう。
どこかに匿名のメッセージを書くとか?
いや、彼女がそれを読んでくれる可能性は低い。他の人間に届いてしまう可能性もある。
そうだ!モールス信号はどうだろう?「トトートー、ツーツツツー」ってボールペンで机を叩けば!
おいおい。誰がモールス信号なんて知っているんだよ?
人とコミュニケーションを極力とらないで学園生活を送ってきた僕は今となってそのことを深く後悔した。
僕は孤立無援のハードボイルドな探偵そのものだった。誰にも助けを求めることはできず、数少ない証拠品から犯人を特定しようとしていたのだ。同時にSFやオカルトに通じるスピリチュアルな気分も味わっていた。
時々感じるその視線だけが、色彩を欠いた死にそうなくらい退屈な学園に灯りを灯してくれていた。
だが、何も打つ手を見出せないまま、時間はいたずらに過ぎていった。
通算700本目の映画を見終わり、自分の部屋の本棚が映画関連書籍で埋まったその年の暮れ。
午前中の授業が終わった時のことだった。
映画批評の本を取ろうと机の中に手を入れると、僕の机の中から見慣れないものが出てきた。
それは味気ないクリーム色の封筒だった。事務用品というほど味気ないものではなく、まわりの女子たちが使っているようなファンシーなものでもなかった。表面がほんの少し粗く、指でなぞるとざらざらした。
封筒の表面にはなにも書かれていない。中に手紙が入っているようだ。封筒越を蛍光灯にかざすと中の手紙の文字がうっすら透けて見えた。
僕は慎重に封筒から手紙を出した。
疑い深い僕がまず気をつけたことは「安易なリアクションをとらないこと」だった。
これが誰かの悪ふざけということもありうる。普段クールに努めている僕がいきなり舞い上がって小躍りでも始めたらそれこそ嘲笑の的だ。
中にはこう書かれていた。
「わたしに
“そんなに僕のことが好きだったなんて知らなかったよ”
と言ってください」
と書かれていた。
僕は意味がわからず困惑した。これはいったいどういうことなのだろう?
今まで見た700本の映画の中からこの手紙の回答に見合う行動や言動を必死になって探ってみたが模範回答は導き出されなかった。
昼休みを告げるチャイムが鳴った。
それと同時に多くの生徒は教室から出て行った。まるでそれらの生徒がフラッシュモブでも興じているかのようなタイミングで一斉に席から離れていった。
水中に押し込んだビニール製のボールが勢いよく水から飛び離れるイメージが頭に浮かんだ。もしくは動物園のすべての檻を開け放つ、そんなイメージも。
バタバタと廊下を駆ける音が聞こえた。学食の日替わりメニューは数量限定のため、そこで昼食を済ませる生徒たちが急いで向かうのはいつものことだ。
ガタガタと机を引きずる音が聞こえた。女子たちは待ち合わせをするようにして互いのクラスを行き来したあと、一緒に昼ご飯を食べるグループを作るのだ。
購買でパン買ってきた男子生徒の声とビニール袋がこすれる「クシャクシャ」という軽い音が教室の外から聞こえた。彼らは屋上へ行くのだろう。こんな寒いのに物好きなやつらだ。
教室に残った生徒はがさごそとバッグから自前の弁当を取り出した。
だいたいこれらの生徒の割合は同じだった。教室で一人で弁当を食べている人間は僕一人しかいない。
スピーカーからエリック・サティの「ジムノペディ」が流れてくるのがわかった。冬にぴったしの曲だ。こんな騒々しい学校でも落ち着いた気分になれる。どこか悲しくて、今の僕の気持ちにそっと寄り添ってくれる。
いつもの耳障りなポップミュージックじゃなくて本当によかった。
今日ばかりはこの選曲をしてくれた誰かに感謝せずにはいられなかった。
ふと、
後ろに誰かが立っていることに気がついた。
そしていつもの視線を感じる。
それもこんな至近距離で。
僕は背筋を伸ばし、そろそろと立ち上がった。手にはさっきの封筒が握られている。
後ろを振り返えると、そこには一人の女の子が立っていた。やっぱり僕の予想は正しかった。
背丈は150cmちょっとで僕の胸くらいまでしか身長がない。髪の毛は染めておらず、蛍光灯の明かりを反射して額から少し上がハイライトになっていた。顔を覆うようにして髪の毛を垂らすボブスタイルで、前髪は軽く揃える感じ。
少し汚れた校内ばきに紺のハイソックス。校則で定められた丈のスカートにカーディガン。前のボタンは全部閉めている。ベタなイメージだけど図書委員でもやってそうな格好だった(実際、彼女は本当に図書委員だった)。
化粧っ気のない顔。端正な顔立ちで目や鼻は整っているが、意志の強そうな太い眉をしていた。
僕の目の前にいたのはそんな日本的な顔立ちの女の子だった。
彼女は口をしっかりと結んだまま、無言で僕のことを見つめていた。
目は真っ直ぐに僕の目を見ている。
こういうときに思うのは人間、人の目を見るときにはどちらか片方の目しか見れないんじゃないだろうか?ということだ。
「人の目を見て話せ」とはよく言うが、そうしようと意識するとどちらか片方の目に集中せざる得ない。それとも僕は目の奥にあるものを凝視し過ぎなのだろうか?瞳の色とか?
彼女の瞳は薄い茶色をしていた。いつまでもじっと見ていたい、僕はそう思った。
だが、いつまでもこうしているわけにはいかない。何か口にしなくてはと思ったときに、あの手紙に書かれていることを思い出した。
僕は彼女の目を覗き込んだ。視線は泳がない。
自分がなにを口にするかで状況はよくも悪くもなりそうに思えた。
覚悟を決めると、少し深めに息を吸って声帯を震わせた。
「あぁ、そんなにも僕のことが好きだったなんて知らなかったよ」
自分の声が自分のものであるように聞こえなかった。
乾いていて最初の音がかすれていた。自分の声なのに情けない気持ちになった。もし外国人が僕の言葉を聞いてそれを文字に起こしたとしたら、きっとその台詞の最後には疑問符がついていたことだろう。
僕がそのセリフを言い切るとそこに沈黙が訪れた。
それは完璧な沈黙だった。そこには外部からの音が入り込む余地はなかった。教室の中で僕たち二人の間に流れる時間が膨張するのがわかった。きっとアインシュタインもこの感覚を味わっていたんじゃないかと僕は今でも疑っている。
彼女は僕のことばを聞き終わると、一瞬眉をしかめた。頭の中でそのセリフを反芻し、一文字一文字を何かのフィルターにでもかけているようだった。
はぁ..。
自分でもわかっていたさ。こんな馬鹿らしいセリフを言う自分の愚かさを。どんなに傲慢なヤツでもなかなかこのセリフは言えないんじゃないかな?
これで僕は残りの一年間を笑い者として過ごすことだろう。
彼女はしかめた眉を元に戻すと、口元をほころばせて、いたずらっぽく笑ってこう言った。
「「そんなにも」の「も」はいらない」
と。
—————–あとがき—————-
ブログ書くことが見つからなかったので、
(いや、まぁ、あることにはあったんですけど、あまりに些細なネタすぎて)
何の気なしに最初の一文を書いたらあとはスラスラと勢いで書けちゃいました。
セガールくんと女のコはその後一体どうなったかは読んだ方の想像にお任せします♪
うまくいくといいね!
【告知】
2016年9月30日、夜18時より目黒駅の近くにある撮影用のセットで開催される「路地裏Dining」にて、路上似顔絵屋さんやります!くわしくはコチラ。
美味しいケータリングのお店が出るので仕事帰りにふらっと立ち寄ってみてください♪
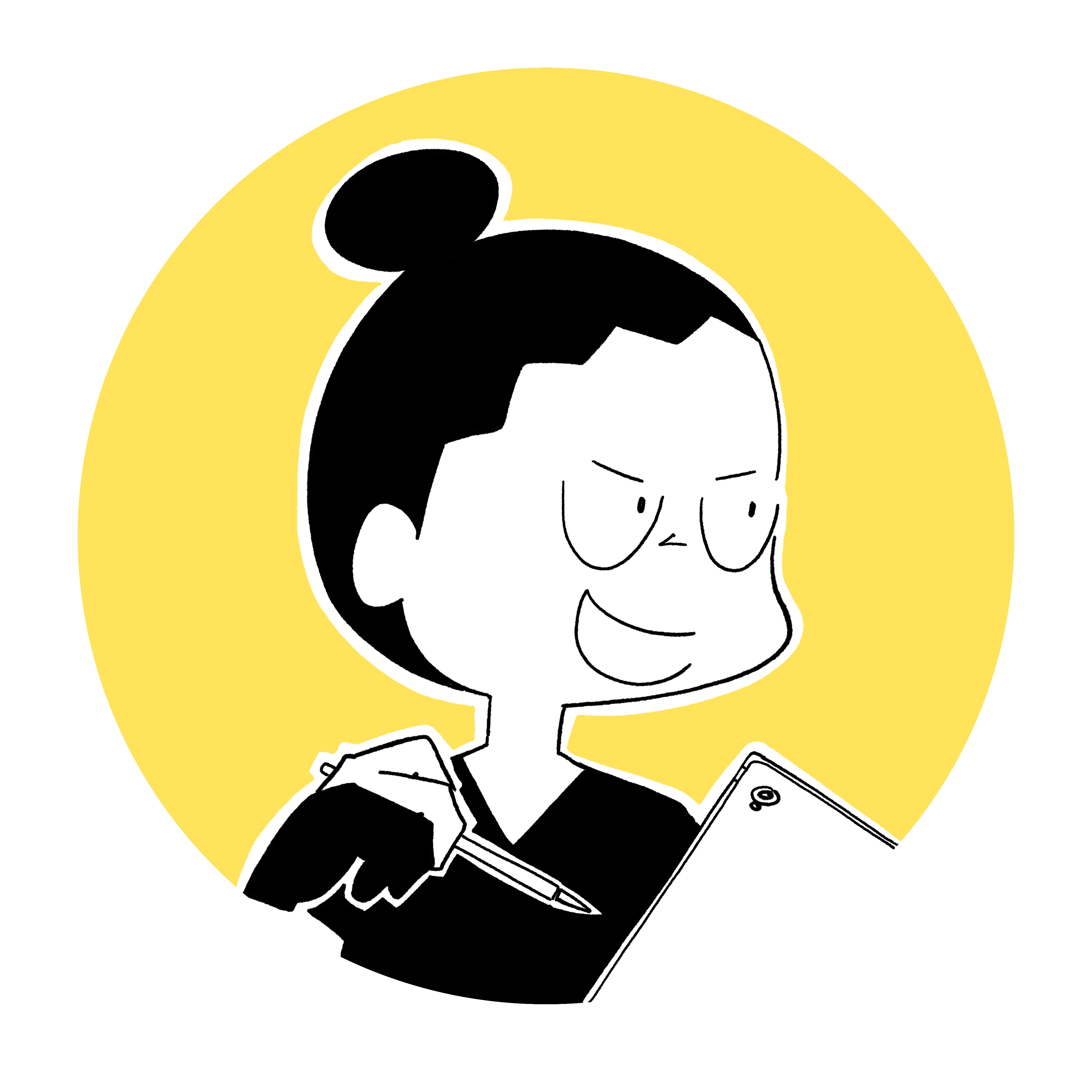

小説面白かったです。
高校の描写が懐かしい。。
あとオチが好きです。
漫画化期待しまーす。
>ますこ
ははは。ありがとう。
最初の一文以降はでっち上げのストーリーでほとんど推敲してないから、まぁ、出来としてはあれなんですけど、
面白がってもらえてなにより♪
でも、これで漫画は描かないかなー?