『こんなカフェがあったらいいのにな』
という自分だけの理想のカフェというのは、カフェ好きの人間であれば誰の頭の中にもひとつかふたつはイメージがあるはずだ。
僕だってそうだ。
完璧なまでの自分の理想のカフェ。
そういうパーフェクトで完全無欠な存在のカフェが果たしてこの世に存在するのかは分からない。だが、そのようなものが見つかった時には、陳腐な言い方をすれば「宝物でも見つけたような幸福な気持ち」になるのかもしれない。
そして、その時に自分が何を思うのかは、実際にそのカフェを探し出してみないことには分からないだろう。
「完璧なまでの自分の理想のカフェ」のことなどすっかり忘れ去ってしまった時に、僕はたまたまそのカフェに出くわした。
そのカフェはまるで僕を待っていたかのようにニョキっと出現した。長い雨が降ったあとで地面からキノコが生えてくるみたいに。
店舗そのものは決して大きくはなかった。
だが、その大きさが親しみやすさを感じさせた。まるで仲のいい友達の家に遊びに来たような気にさせてくれる。
植物がふんだんに使われており、一番目を惹くのは屋根に敷き詰められた草木だ。どこか気持ちの良い原っぱを切り取って、そのまま運んできたような、手入れの行き届いた綺麗な屋根をしていた。窓際に飾ってある花々も配色を考えて飾られているのがうかがえる。
看板は店の顔でもある。看板を見れば、その店がどのような人間によって作られたのかが知ることができる。
見たところ、素材やデザインから手作りだということがわかる。木の切りそろえ方やペンキの色合い。人の手によってにしか出せない独特の温かみを感じる。
店の外観に親しみを感じさせる要因は他に、外に置かれている小物が店の人間の生活感を反映しているせいもあるだろう。
きっとオーナーは整理整頓の好きな人間なのだろう。変な言い方をすれば「あえて道具を片付けないでおいている」と言ってもいいかもしれない。もしかしたら店の人間は作業台においてある工具も装飾の一部として考えているのかもしれない。サーフボードが立てかけてあった。僕は一瞬でこの人の人柄を好きになってしまうかもしれない。僕はマリンスポーツはやらないが、趣味が合いそうだなと思う。
入り口のドアを引いて店の中に入る。
中に入ると想像していた以上に店内が広々としていることに気づく。天井を高めに作っているからだ。頭上ではファンがゆっくりとまわっている。
挽きたてのコーヒーの匂いが香る。そしてBGMがさりげない音量でかかっているがわかる。英語の歌詞だ。それは最近のヒットソングじゃない。10年以上の時を隔ても人々に聴かれ続ける良い音楽だ。曲が自然なタイミングで切り替わり、ジャズがスピーカーから流れ出した。そんな時は時間がいつも以上にゆっくりと過ぎていくのが感じられる。
そのような情報を僕は五感を通して瞬時にキャッチする。『あぁ、ここは想像していた通りに居心地の良さそうなカフェだ』と即時に理解するのだ。
そしてカウンターに目が向く。
レジを置く代わりににパソコンやタブレットを用いているのを見ると最近できた店のようだ。
カウンターの前には手作りのクッキーやチョコレートが大きな瓶の中に入れられて綺麗にディスプレイされていた。マフィンやケーキはガラスのショーケースに並べられており、ガラスには白いインクで可愛い絵が文字が描かれている。視覚的にもワクワクさせてくれる店みたいだ。
他にもカウンター周辺には近々地元で開催されるイベントのフライヤーや他の店のショプカードが置いてあるほか、雑貨もいくつか売られている。どうやら店主が海外で仕入れてきたものらしい。
カウンターの向こうにいるマスターと目が合うと、ニコっとあたたかい笑顔を返してくれた。
それは馴れ馴れしいというわけでもなく、サービス過剰というわけでもなく、適度な距離感を保った心地よい客と店の人間との距離感だった。
カウンターの向こう側には黒板にメニューが書かれている。
個人でやる店なのでそこまでメニュー数は多くない。ドリップ・コーヒーから始まり、エスプレッソやアメリカーノ、マキアートやカフェラテなどが揃っている。品目は少ないが豆にはこだわっているみたいだ。エクアドル産やコロンビア産の豆の他、日替わりの「Today’s Coffee」というのもあった。どうやら今日はケニア産のコーヒー豆でドリップコーヒーを淹れているみたいだ。オススメに弱い僕は迷わずそれを注文する。
コーヒーはマグカップに注がれて出てきた。
カップには店の名前とロゴが描かれている。シンプルなデザインだ。
マスターはマグカップを音を立てずに「そっ」とカウンターに置く。僕は礼を言ってそれを受け取った。
カウンターで渡されたコーヒーを見ると僕は心を弾ませてしまう。安いコーヒーを飲もうと思えばいくらでも飲むことができる。だが、産地直送の豆を使って人の手を通して入れられた職人的コーヒーは決して安いわけではない。カフェでそのようなコーヒーを飲むことは僕にとって一種の贅沢でもある。
だからこそ僕はコーヒーを飲むことはもちろんのこと、カフェにいる時間というものを隅から隅まで堪能したいと考えている。
心なしか口元が緩む。
早く席について冷めないうちにこのコーヒーを飲みたいが、意識的に心を落ち着けて歩調を緩め、コーヒーの中身がカップからこぼれないように努める。
受け取り口の脇には通常のミルクの他にロー・ファット・ミルクやソイ・ミルクが置いてある。砂糖はブラウンシュガーの角砂糖でひとつひとつが包み紙に包まれている。
僕はソイ・ミルクをほんの少しコーヒーに注いだ。
室内は木調だ。
見た所テーブルや椅子、床や屋根を支える梁までも木でできているみたいだ。店の一角には薪ストーブが設置してある。コーヒーの香りの他に木の匂いも鼻をくすぐる。
店を店の壁には絵の他に趣味のいい雑貨も飾ってある。何点か写真も額縁に入れられて吊るされている。アイスランドの写真のようだ。日本にはない種類の壮大な自然が写真の中には広がっていた。
エスプレッソマシーンがスチームを出す「プシュ〜〜ッ…」という音が聴こえる。誰か他の客がオーダーしたコーヒーなのだろう。
僕は窓際の席に座ることにした。
まだ昼前の早い時間で店は混んでいない。もし混んできたのであればその時席を移動すればいいだろう。
窓際の四人掛けのテーブル席は作業をするにはうってつけだ。そこから眺めのいい景色が見えた。テーブルの下を覗けばさりげなくコンセントもあったりする。iPhoneのバッテリーが残り少なくなってきているのでちょっと電源を失敬しよう。店員は嫌な顔ひとつしない。ありがたい。
テーブルにつくと、僕は鞄を下ろし、窓際に腰を下ろした。
その空間に自分を馴染ませるように一呼吸置いて窓の外を見る。
つい5分ほど前まで自分が歩いていた町なのに、カフェの中から見るとなんだか少し違って見えるような気がする。まるで自分が旅をしていいて、どこか知らない国の知らない町にあるカフェにやって来たかのような錯覚を受ける。
僕は思い出したかのようにマグカップに手を添える。
コーヒーの最初の一口を飲むということは、僕にとっては儀式のようなものである。
最初の一口は大げさに言えば僕とコーヒーとの邂逅だ。
チェーン店やしょぼくれた店を除けば、同じ味のコーヒーというものはこの世に存在しない。
コーヒーは焙煎により風味が変わるので、同じ産地でも誰がコーヒー豆を扱ったかによって味が異なると聞いたことがある。
だが僕は味覚に関しては平々凡々の域なのでこれは感覚的な問題だろう。
コーヒーとは僕にとって味だけではなく、空間やそれを提供する人によって決まると考えている。どんなに高級な豆から抽出されたコーヒーでも、それを扱う人間が粗雑な人間であれば、そのコーヒーの持つ価値は薄れてしまうだろう。
「インドで飲むチャイはインドにしかないのだ」という友人のセリフが僕にはわかる気がする。インドには行ったことがないけれども。
コーヒーを一口すするとケニア産のコーヒー豆の酸味がわずかに口の中に広がっていくのを感じた。喉の置くへ濃い液体が染み込んでいく。インスタントコーヒーや缶コーヒーでは味わえない感覚だ。
個人的なささやかな儀式を終えると、僕は鞄から読みかけの本をとりだした。
ブックマーカーが挟まっているページを開き、それからもう一度コーヒーをすすると、僕は本の中の世界へと入っていった。
京都に住む大学生が意中の後輩の心を射止めんと奮闘する話だ。少し頭の固い真面目な学生が不器用までに恋に奔走する姿は読んでいて微笑ましい。かつての自分に多少なりとも重ね合わせてしまう。
20ページほど読みすすると、僕は読書を中断し顔を上げてコーヒーをすすった。コーヒーは受け取った時ほど暑くはなかったが、それでも美味しいコーヒーは冷めても美味しいままだった。
窓の外の景色を見渡す。3分くらいぼうっとしていると、聴覚がほんのわずかに敏感になる。
店内にはBGMの他に、小さいけれど様々な音で溢れていることに気がついた。
「カチャンカチャン」というカップとソーサーが当たる音、エスプレッソマシーンがコーヒーを淹れる音、僕以外の客の話し声、快適な室内温度を保ってくれる静かなエアコンディショナーの音。
他にもなんの音かはわからないけど、心臓がトコトコいうような人間味のある音を感じた。
もしかしたら、店も呼吸をしているのかもしれない。人間とは違ったシステムで生きているような気がしてきた。
僕がこのカフェに感じる親密感はそのせいなのかもしれない。
そんな突拍子もない妄想をした後で、
僕は君のことを考える。
君がそばにいてくれたらどんなに幸せだろうなって考える。
今この瞬間に僕の真向かいの席に座って僕と同じように本を読んでるだけでも最高だろうな。「ねえ、ちょっとマフィンでも食べたくない?」なんて言ってお互い別々の種類のマフィンを買ってさ、わけっこしながら食べたら、きっと満ち足りた気持ちになれるだろうな。
君のことを思うと、心がじんわりと温かくなるのを感じる。それは淹れたてのコーヒーを飲む時の感覚ににている。
今は何をしているんだろう?なんて考え出すと、僕はもう本なんか読んでいられなくなっちゃうんだ。自分でもね『ばかだなぁ』って思うんだけど、これだけはどうしようもならないや。
そして
しばらく自分に都合のいいことばかり考えたあと、
『じゃあ、僕に何ができるだろう?』って自分に問いかける。
僕に何ができるんだろう?
この閉じられた世界は、一見無限の可能性が広がっているように思えて、選択肢は自分の想像していたほど多くはないことに気づく。
自分たちが恵まれた世界、国、地域や町に暮らしていることは重々承知だけど、僕は自分が前に進めば進むほど、自分の前に開けていた道の幅がどんどん細くなっていくようにすら感じる。
「僕は君に何をしてやれるだろう?」
たぶん、
取り返しのつかないことや
損なわれてしまったことが僕たちの間にはたくさんあったし、
傷つけ合ったことも何度もあったと思う。
お互いにうんざりして愛想をつかすことだってあったんじゃないかなと思う。
それでも僕はそれをひとつの終焉だとは思わない。
あの時の君の言葉を僕は嘘だとは思わない。
僕のダメなところと君のどうしようもないところは、きっと相対的に比較してみれば同じくらいなパーセンテージで表されることだろう。
でも、僕たちはそれを受け入れてなんとか二人でやっていくしかないんだと思う。
いや、二人だったら乗り越えていけるはずだと僕は信じてる。
たぶんこんなことを言うと君は鼻で笑うんだろう。
「何をいまさら」と失笑するんだろう。
そんな僕の姿が情けなく思えたら肩に思いっきり正拳突きを喰らわせてくれてもかまわない。
世界を一周させるがごとく長大な距離の思考を壮大なスケールでドラマチックに一周させたあと、
僕は自分が一人じゃないことを思い出した。
———————あとがき———————-
ちょっと前にツバサさんが使っていたコピックカラーを譲ってもらった。
そのお返しに僕はイラストを描いた。
それで今日郵送した。明日の午前中に届くらしい。
美味しいコーヒーを出すカフェって話をしたかっただけなんだけど、
なんだかか短編ができちゃったな。
うん。美味しいコーヒーが飲みたい♪
あ、明日から4日間、朝霧JAMにスタッフとして行ってきます。見かけたら声をかけてください。
それではよい週末を。
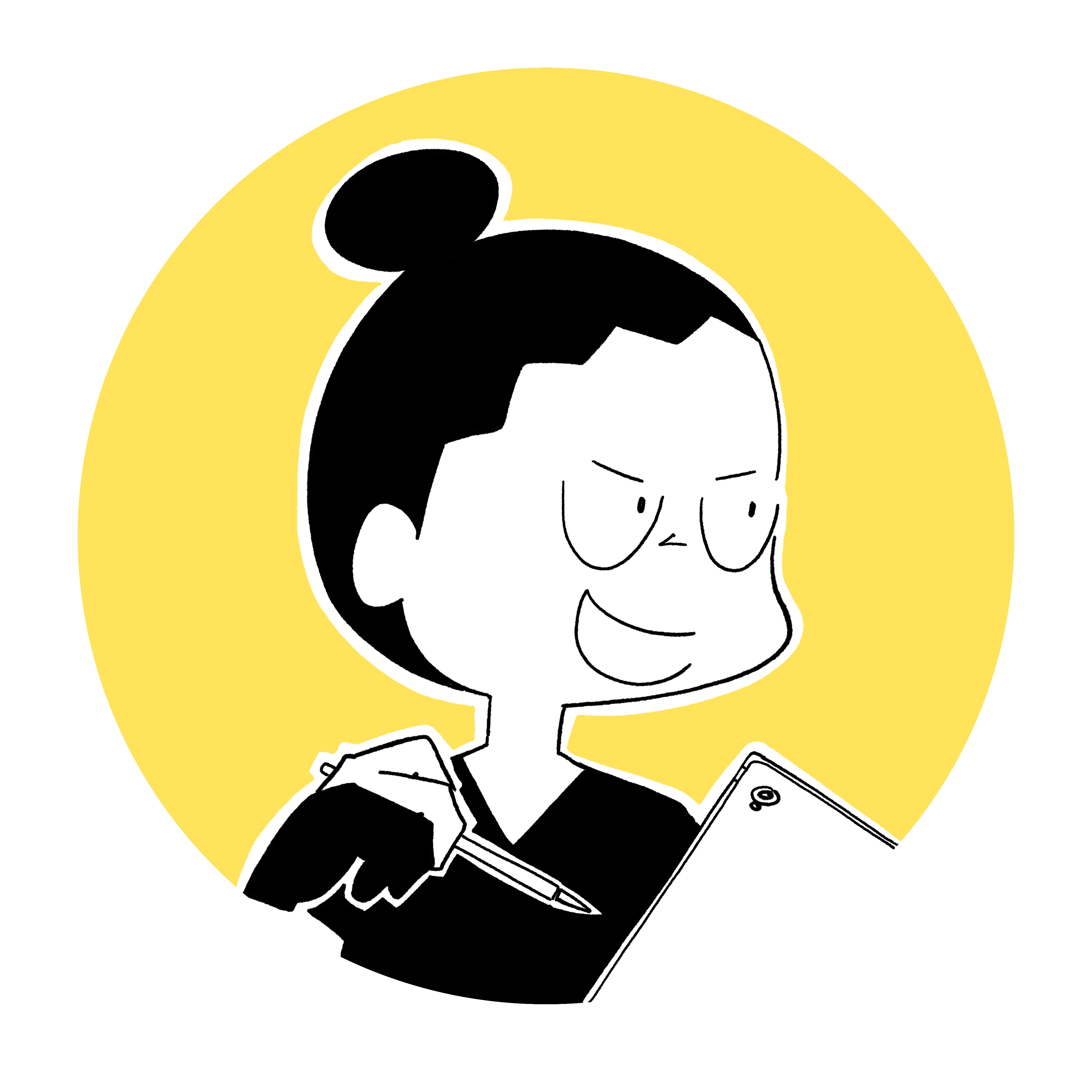

コメントを残す