▷11月27日/パタゴニア、ヴィラ・オヒンギンズ
「明日ハイキングに行くけど、シミも行く?」
そうマックは僕に尋ねた。
正直言うと僕はあまり気乗りしなかった。なぜなら明日から36kmの道のりを歩いて国境を越える計画だったからだ。
どうして、その前日に体力をすり減らすようなことをする気になれるのだろう?過酷な砂漠マラソンに二度も出場するどMなマサトさんならともかく…。
それでも僕は流されるように「行きたい」と言った。
こういうのはチャンスのひとつだ。きっと面白い経験ができるんじゃないかと思ったからだ。
なぁに、しんどいのは最初の30分だけさ。
朝6:30に誰かのアラームが鳴り、マックとマサトさんがゴソゴソと支度をし始めた。
僕はボサボサ頭を掻くと、パンツを穿きショルダーバッグにペットボトルや眼鏡など簡単なものだけ詰め込んだ。
出発前にマックがコーヒーミルで淹れたコーヒーとバナナが入ったオートミールを用意してくれた。お礼を言ってそれを胃に流し込むと、僕たちはひんやりとする外に出た。
ハイキングコースは村のはずれから始まっていた。いきなりの階段だ。
宿の敷地内にいた二匹の犬が僕たちを抜かしていった。ここの飼い犬はとても自由に思える。
階段を上りきった後は林が続いていた。高さがあり、辺りは木々で覆われてあるため、林の中には太陽の光は少ししか入らなかった。ジメジメとしたトレイルをマックを先頭に僕たちは歩いた。
先ほどの二匹の犬は僕たちは先頭をトコトコとかけていった。
「ねぇ、飼い主のいない犬って”Strey dog”でいいの?」
僕はマックに尋ねた。
「あぁ、そうだね」
「”wild dog”とは違うの?」
「えーっと、”wild”とは言わないね」
「狼とかそういうの感じだ?」
「まぁ、そんな感じだよね」
二匹の犬はまるで山犬の様に見えた。それほどまでに辺りを元気よく駆け回っていた。
やがて林が終わると、今度は丘を登るような道に変わった。坂道を登ると息が切れる。
二匹の犬はまだ僕たちと一緒だ。一体どこまでついてくるのだろうか?
二頭のうち一頭は明らかに僕たちのことを待って進んでいた。ある程度まで先を進むと、ちゃんと座って僕たちのことを待っているのだ。

急な丘を登り終えると、トレイルは山道へと変わった。30分も経つ頃には体が慣れてきて、坂を登っても息切れしなくなってきた。
ぺちゃくちゃと喋りながら歩く余裕も出てきた。僕はいつものようにくだらない冗談を飛ばして二人の笑いを誘った。
山道はジメジメしており、泥に足を取られないように歩かなければならない場所もあった。泥道や水たまりを避けるようにして歩いた。
一時間くらい歩いたところで、とうとう僕はコケて左手を擦りむいた。
左手から着くような形で転んだため、手首が少し捻挫のように痛めてしまった。
僕は『もしかして骨折したんじゃないか⁈』とネガティヴな考えが頭に浮かんだ。
そして、すぐにその可能性を取り下げた。骨を折ったのであれば一気に腫れ上がり、その箇所がほとんど動かなくなるからだ。
僕は高校一年生の時に自転車で転倒して右腕の骨にヒビを入れたことがあった。その時の体験を思い出して自分を安心させた。
思えばこの二年五ヶ月の旅の中で、風邪をひいたり、盗難に遭うことはあっても大怪我をするということはなかった。
それを考えると僕は何かに感謝せずにはいられなかった。
そうだよな。ちゃんと日本に帰るまでが旅だもんな。
左手の擦りむいた箇所からは血が流れていたが、そのまま放っておくといつの間にか血は止まっていた。

途中雪解け水が流れる場所をいくつも通り過ぎた。僕は500mlのペットボトルに水を補充した。
マックは持っていたボトルに水を入れると、電動歯ブラシのような機械を水につけるとそのままの体勢でストップした。どうやらそれは赤外線でバクテリアを殺菌する機械らしい。
マックは日本でカテゴライズされるような「アウトドア男子」という感じはしないが、持っているものはいいものばかりだ。グレゴリーのバックパックは新品で新しいロゴだった。
やがて山道が終わり、僕たちは川の上流に向けて歩くような形になった。
今日のハイキングのゴールは氷河の見える場所まで行くことらしい。
そういえば昨日の夜、マックが他のツーリストにそんな話をしているのを思い出した。
犬は相変わらず一定の距離を保って僕たちの先を歩いていた。
僕が何度かパン切れを与えるとすっかり懐いてしまったようだ。桃太郎が仲間を集めた時もこんな感じだったのだろう。意外と動物を手なづけるのは簡単だ。
何度かトレイルを見失う時もあったが、そう言った場合は犬たちが先を歩いてくれているのが目印になることもあった。ナビーゲーターの役割を犬たちは果たしていたのだ。
三時間ほど歩くと僕たちはトレイルとは呼べないような険しい道を歩いていた。
本当にこの先に氷河があるのか分からないままマックを先頭に川の上流へ向けて歩き続けた。
二頭いたうちの一頭はついに僕たちについて来るのを諦めてしまった。それでも黒い雌犬だけが一生懸命僕たちについてくる。
そしてとうとつ僕たちは先に進めなくなった。
川の流れは速く、両側は急な斜面で阻まれている。
何度か斜面を歩こうとトライしたのだが、砂利が多いため足が滑って進むことができない。体重の軽い犬だったら先に進めそうな気がした。
最初は天気の良かった空も徐々に曇り、雨もパラつくようになった。
「これは先に進めそうもないね。残念だけど氷河は見れそうもない」
マックはそう言った。

僕たちは再び元の道を引き返すことにした。
急な山肌を落ちないような慎重に足を運んでいった。
最後の最後で僕は足を滑らせ、岩に首を打ち付けた。肘には縫ったような傷跡ができ、右手の中指と薬指の第一関節がいくらか腫れていた。満身創痍だ。
帰りは三人とも口数が少なくなっていた。
雨が降った後に別のハイカーが道を歩いたようで、トレイルは泥があちこちでこねくりまわされていた。そのため足を濡らさずに歩ける場所を探すのに苦労した。
何度も泥水に足を浸し、サンダル履きの僕の足はぐしょぐしょになった。
犬も疲れたそうに尻尾を下げて歩いていた。
16:00前に村に戻った時、僕は達成感というよりか、解放感のようなものを味わった。無性に日本のラーメンが食べたくなった。
一度宿で休むと、明日の移動のためのフェリーのチケットを買いに行った。44000ペソ(¥7,606)もする高額なチケットだった。
僕が一番見たいフィッツロイまでの道のりは長く険しく、そして金がかかる。
チケットオフィスから出ると、先ほどのハイキングで作った首の傷から血が流れているのがわかった。痛みはないのでそれほどひどくはなさそうだ。
マサトさんは「消毒をしよう」と僕につきあってくれた。
僕がマサトさんにアルコール消毒をしてもらっていると、トルテルで顔を合わせたフランス人の姉妹の姉の方が「私は医者よ!」と言って、傷の手当をしてくれた。なんだかこういうのってすごく頼もしいなと僕は思った。
傷の手当が済むと、今度は三人でキャンプで食べる二日分の食料の買い出しに向かった。
マックは必要な食材を書き出した紙を手にウンウンうなっている。
僕たちは三人はキャンプ用のガスバーナーを持っていない。となると、作れるものは限られてくる。
各々に必要な食料を買い、あとは宿でオニギリを作ることになった。具材はツナマヨネーズだけ。
マサトさんが鍋で1㎏の米を炊くとかなりの量になった。熱を冷ましいつもの三角の形に整えていった。
マックは「これがライス・ボールだろ?」と言って球体のオニギリを作ってリタイアした。
日本人のDNAが作用しているのかどうかは分からないが、僕もマサトさんも慣れた手つきで三角形のオニギリを作ることができた。
それだけ済ませてようやく僕は今日を終えることができた。
八時間にも及ぶハイキングでヘトヘト。裂傷に打撲。明日が本番だってのに…。
さて、明日はいよいよ国境越えだ。そしてその先にはフィッツロイがある。

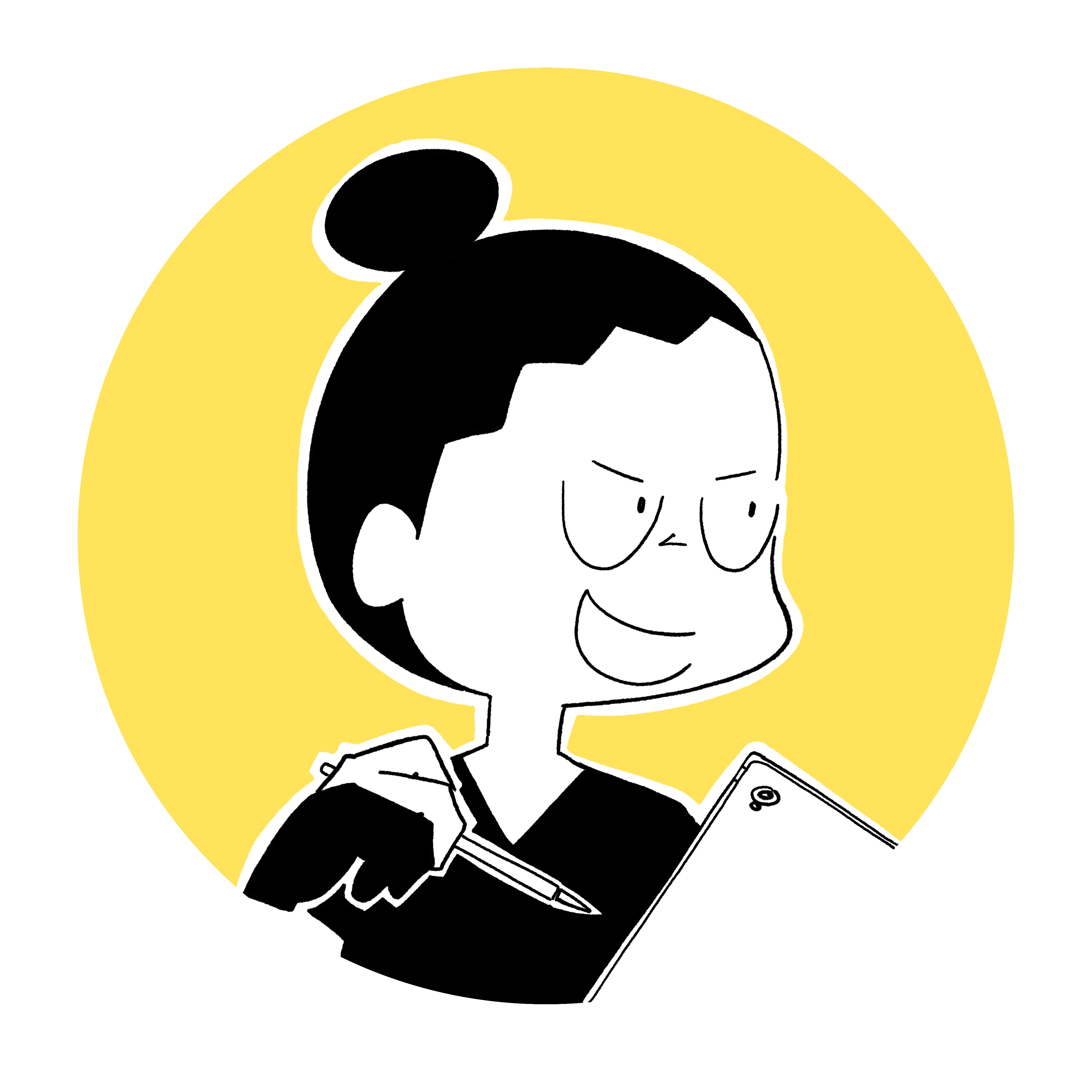

コメントを残す