▷12月2日/アルゼンチン、エル・チャルテン〜エル・カラファテ
朝7:00に起きた。
南半球に位置するチリは春が深まりつつある。三寒四温なのか、ここ数日は暖かくなってきた。外に出てもそれほど寒さを感じなかったが、空には薄い雲がかかっていた。昨日の天気とは大違いだ。
僕とマサトさんは宿を出ると町外れまで1.3kmの距離を歩いた。通りにはほとんど人が出ておらず静かだ。
途中にあったごみ箱からダンボールを頂戴した。食べ物の油汚れが少しついていたが、使えないほどではなかった。
そして町外れに出ると僕たちはそこに荷物を降ろした。
「じゃ、マサトさん、行き先を書いてください♪」
僕はギターケースから似顔絵用の太いマジックをマサトさんに差し出し、ニッコリ笑ってそう言った。
マサトさんは「EL CHALTEN」と大文字で書くと左上にハートマークを書いて斜線で塗りつぶした。
0円から始まる移動、ヒッチハイクの始まりだ。
僕たちはが準備をしている間にすぐ横のバスターミナルからツーリストたちを乗せた大型バスが出て行った。乗客たちは僕たちのことを訝しげに見ていた。
そんなことを気にせずに、僕はマサトさんにボードを持たせて車道に少し出るような形でポジショニングをした。

町の方からボチボチと車が走ってくるが、直前の曲がり角を曲がる車がほとんどだ。
エル・カラファテへと続く道は一本しかなく、ここを通る車は間違いなくそこへ行くように思えたが、ドライバーたちは「そこへは行かないんだ」とハンドサインで応えた。
時間が経つごとに風が強くなっていく気がした。太陽が出ればどれほどヒッチハイクがやりやすいだろうか?
マサトさんはどうしてか、上は薄手のジャケット(アタカマ・マラソンでもらったやつらしい)と下はハーフパンツといった格好で「寒っ…」とか言っている。二ヶ月前から沿っていないという髭はマサトさんの顔を浮浪者っぽく見せていた。
僕たち二人は運転手からどんな風に見えるのだろうと、僕は疑問に思った。
40分くらいが経過した時に一台のキャンピングカーがジェスチャーで応くれた。「目的地まで行くけど、一人しか載せられないんだ」
「これで成功率は50%ですね!」そう言って僕たちはヒッチハイクの成功に希望を抱いた。
時間が経つごとに車の数が少なくなってきたような気がした。
ラ・フンタでの悲劇を思い出す。やっぱり車の少ないパタゴニアでヒッチハイクなんて成功しないんじゃないかと僕は思い始めた。
僕がマサトさんをヒッチハイクに誘ったのだ。今日の目標は無事ヒッチハイクを成功させて、マサトさんにヒッチハイクを楽しんでもらうことだった。
このまま無理に時間を浪費しても仕方がない。エル・カラファテ行きのバスは12時が最後らしかったので、僕は「あと一時間粘ってダメだったらバスに乗りましょう」と提案した。
ちなみにここからエル・カラファテまでのバスの値段は30ドル。距離にして250km。インフレ真っ盛りのアルゼンチンな物価が高い。
そろそろ二時間が過ぎようとした時、もう僕は諦める直前だった。
そんな時、一台の車が止まった。中には三人の女性が乗っている。
これは成功か⁇
それとも「途中まで」のパターンか⁈
小走りで運転席に駆け寄ると、助手席の扉が開いた。グレーのスウェとパンツにTシャツ、大きなサングラスをかけた若い女のコが「乗りなさい!」と元気よく行った。
「あ、あの!エル・カラファテまで行くんでしょうか⁇」
「もちろん!」
「うわぁあああああ〜〜〜〜‼︎‼︎」
僕とマサトさんは歓喜の声を上げた。
トランクにはバックパック一個分しかスペースがなかったので、荷物を膝の上に置くことになった。
僕はギターの安全が最優先なので(かつてカナダでヒッチハイクした時にトランクを閉めた際にネックを折っている)マサトさんには申し訳ないが、バックパックはトランクに入れさせてもらった。
ドライバーはアンジェラというドイツ人の女性だった。
ブエノスアイレス在住で旅行代理店で働いている彼女たちは、車を二台借りて、三日間だけパタゴニアを旅行しているそうだ。今日がその最終日らしい。
まさか、そんな社員旅行で僕たちを拾ってくれるだなんて!
隣に座っていた女のコはもう一台の車へと移動していった。おかげで僕たちは後部座席にゆとりをもって座ることができた。
アンジェラは「グッド・カルマよ♪以前私もガソリンが切れて動けなくなってた時に誰かに助けてもらったことがあるの。今回はそのお返しよ」と言った。
こういう考え方は好きだ。また僕たちも受けた優しさを誰かに返していきたい、そう思った。
車の中では、まるで大きなパイプを吸うように、僕たちはマテ茶をいただいた。
一本道は綺麗に舗装された二車線の舗装道路で景色はスルスルと流れていった。
アンジェラが言った。
「私たちペルト・モレノの氷河を見に行くんだけど、もしよかったらあなたたちも一緒に行く?」
それを聞いて一気にマサトさんのテンションが上がった。
「シミくん、おれらマジでラッキーだよ!だって氷河まで行くのに交通費だけで5,000円以上かかるよ!それが入場料だけでいいなんて!」
「これはーー…、流れに乗りましょう!」
まさにツキの流れがやって来た。僕たちはアンジェラたちに同行させてもらうことにした。
エル・カラファテまでの道のりは軽快にお喋りを楽しんだ。というのも、旅行代理店に勤めているだけあってアンジェラたちは英語が喋れたからだ。
ギターを弾いてよとリクエストされたので、いつもの鉄板曲を疲労すると、二人ともサビの部分を一緒に口ずさんでくれた。
昼前にはエル・カラファテに到着した。アンジェラは車を縦列駐車すると、スーパーに向かった。
僕たちはそこでトイレや食糧を買っておいた。フィッツロイのあるエル・チャルテンの町よりも物価が下がったような気がした。
車が再出発すると、アンジェラが申し訳なさそうに言った。
「これから氷河を見に行くわけだけど、私たち一時間しか滞在できないの。今日のフライトでブエノスアイレスまで戻らなくちゃならないのよ。あなたたち、どうする?」
僕はそこまで氷河に興味がなかった。そもそも氷河を見れるだなんて思わなかったからだ。『まぁ、一時間でもいいんじゃないの?』と僕は思った。
エル・カラファテから一時間ほどで氷河のある自然公園へと到着した。
入り口で門番が国籍を訪ねている。どうやらアルゼンチン人価格というのがあるらしい。外国人は入場料するだけで3000円もかかる。
ゲートを抜けると、山道を走った。そこから氷河の一部が見えた時、僕は思わず声を漏らした。そこにはケーキの断面のようは巨大な氷の大陸があったからだ。
駐車場に車を止めると僕たちはシャトルバスに乗り、氷河を望める展望台へと向かった。
シャトルバスを降り、氷河が一望できるデッキへとみんなで歩いていく。アンジェラたちは楽しそうに写真を撮っていた。
彼女たちの滞在はわずか20分しかなかった。すぐにシャトルバス乗り場へと引き返した。
シャトルバスを待っていると、遠くよ方から「ズゴゴゴ…」と雷のような音が聞こえた。
アンジェラの同僚が「今のは氷河が崩れる音だよ」と僕に教えてくれた。ここは氷河が崩れる瞬間を見られることでも有名らしい。
シャトルバスを待っている間、マサトさんは小さな岩の上に登り、氷河を眺めていた。たった20分の滞在じゃ全然満足できなかったんだろう。
バスの中で僕は尋ねた。
「どうします?アンジェラたちの車に乗せてもらうか、それとも氷河おかわりして、またヒッチハイクするか。僕はぶっちゃけどっちでもいいんです。そもそもここに来れたこと自体ラッキーだから。まぁ、氷河の崩れるとこは見たいですけどね。マサトさん決めて下さい」
マサトさんは「う〜〜ん…」と少し悩んでから「もう一回氷河を見に行こう!」と言った。
「ということはまた運だめしですね」と僕は冗談っぽく言った。
正直に打ち明けると、僕はビビってたのだ。国立公園内からエル・カラファテ行きの車が捕まえられるか分からないことに対して。
交通に高いアルゼンチンだ。それならアンジェラたちにまた乗せてもらった方がリスクを回避できる。
駐車場にはまだ何台も車が止まっていた。ほとんどの車がエル・カラファテに帰るはずだ。
アンジェラたちにお礼を言って車を見送ると、バックパックを背負って再びシャトルバスに乗った。
バックパックを背負ってここに来るヤツなんて僕らしかいなかった。ドスドスと荷物ごと移動しデッキの上を歩いていった。その途中、何度か氷河の崩れる音を聞いた。
展望台に着くとそこにはあまり人がいないように思われた。『もしかしたらみんな帰りだしたんじゃないか?』不安が頭をよぎったが今は目の前の氷河を見ることに集中した。
氷河はの内部はところどころ青く、まるで中でライトが光っているんじゃないかというくらいに鮮やかな色を放っていた。
氷河の大陸を目の前にすると、人は無口になるらしい。展望台にいたほとんどの人間は手を手すりに起き、黙って氷河が崩れ落ちるのを待っていた。
僕たちも彼らと同じように氷河が崩れ落ちるのを待ったがなかなかその瞬間を目にすることはできなかった。そこからじゃみえない反対側から「ズドォォォ…」と音が聞こえるだけだ。
一番見晴らしのいい場所で僕たちは氷河が崩れ落ちるのを待つことにした。風は冷たく、雲の切れ間から太陽の光が差し込むだけだった。
アウターのポケットに手を突っ込んで待つ。マサトさんはカメラを構えているが、なかなかその瞬間はやって来ない。
氷河の下の方のごくわずかが崩れた。あまりの小ささにがっくしくる。

「あと10分待ったらやめよう」
そうマサトさんは言った。
ブログで色んな人の写真を見てきたんだろう。それでペルト・モレノに期待をしてきたんだろうな。そう僕は思った。
昨日のフィッツロイのように氷河にもシーズンがあるのだ。僕たちは早く来すぎたのかもしれない。もっと暖かくなってきて太陽が出ている日ならもっと氷河が崩れる回数が多いだろう。
さっきよりは大きい氷河が崩れた。だがそれは僕たちが想像していたものと比べ、大分小さなものだった。
見切りをつけて僕たちは展望台を引き上げることにした。シャトルバスに乗り、駐車場に戻った。またヒッチハイクだ。
駐車場に戻ると僕たちは言葉に詰まった。
車の数が明らかに減っている。そこには10台ほどの車しか止まっていなかった。
「明らかに…車減ってるよね?」
「ダメです!それを言っちゃ!」
それでも僕たちはヒッチハイクをすることにした。
駐車場の出口で僕たちは車を待ったが、それよりも直接ドライバーに交渉する方がベターだと思った。
いつもの要領でにこやかにドライバーに声をかけるが、立て続けに「ノー」と言われる。
そこには僕たちの乗れるスペースがあるのだ。ということは彼らは僕たちを車に乗せたくないというこだ。何もすべての
ドライバーがヒッチハイカーを載せるわけじゃない。彼らにだって選択肢はあるのだ。
3台の車に好意的ではない断られ方をされた。精神的ダメージと焦りがつのる。
『っていうか、おれから胡散臭さ出てるか?』
そう思った僕はマサトさんに交渉に行かせることにした。
ちなみにマサトさんは英語が僕より達者だが、スペイン語がほとんど喋れない。
ハニカミながら浮浪者すれすれの青年がドライバーたちに近づく。手には「EL CALAFATE」も書かれた薄汚れたダンボール。
「E..,Excuse me?」
え、英語だ!
声をかけたのはヨーロピアンっぽさそうなカップル。車種はセダン。
小柄な女性の方は優しい笑顔をしている。長身の男性は無口。ど、どうだ…⁈
「僕たちはエル・カラファテまで戻りたいんですけど、もし目的地が同じなら一緒に乗せてってもらってもいいですか?」
カップルは顔を見合わせる。
「いちわよ!」
「うおおおおぉぉぉ〜〜〜‼︎」
僕は思わず泣きそうになった。
カップルはノルウェー出身だった。彼氏の方は「ソーシャル・アンソロポロジー」という学問を学んでいるらしく、ブエノスアイレスには留学していたそうだ。もう少ししたらノルウェーに帰るらしい。
彼女たちの方は短期で旅行に来ているよう。
どういうわけか、マサトさんに訂正されるまで、しばらく僕は二人の出身地をフィンランドと勘違いしていた。
マジでツイている。やっぱり流れはあった。

無事エル・カラファテへと到着した僕らは宿を探すことにした。
しっか者のマサトさんは宿の場所を調べてあるので、僕は何も心配しなくいい。ヒッチハイクのコーディネートは僕。宿はマサトさん。そんな役割分担だ(笑)
エル・カラファテには安宿はあまりないように思えた。目をつけていた宿のドミトリーは130ペソでおまけに満室だった。
キャンプサイトが充実していたので、こんばんは僕たちはそこにテントを張ることにした。僕のボロテントだ。
そこで何人かの顔なじみと再会することとなった。別の町で会ったチャリダーが何人もいた。
エル・チャルテンで会った女子大生のカレンちゃんもそこにいた。彼女はドミトリーに止まっているらしい。
同室の看板にレタリングを描くアーティストのおっちゃんがバーベキューをするそうで、カレンちゃんはその招待を受けているらしい。
下心満載のスケベオヤジだったので、僕たちには150ペソという宿代以上の値段をふっかけてきたので、僕たちはパスした。
「おれだったらお金とらずに振る舞うけどなぁ。というか、おれはそうでありたいな」そうマサトさんが言った。
スケベオヤジとカレンちゃんとで僕たちはスーパーに行くことにしたのだが、そのオヤジが堂々と万引きをしていることが発覚し、僕たちは残念な気持ちになった。
夕方前の20:30に僕はギターを持って一人スーパーの前に立った。
アルゼンチン初バスキングはどんなもんだろうか?
『っていうか物価高過ぎなんだならその分ウハウハなんじゃね?』
と思ったが、雑念が浮かんではレスポンスはもらえない。
まぁ、肩の力を抜いてゆるくいこうぜ。
こんなこんなで一時間半のバスキングで180のアガリ。2,276円。おお…!
夜、マサトさんと町を散歩してこの日を終えた。
上出来過ぎる一日だ。欲を言うなら野菜が食べたい。

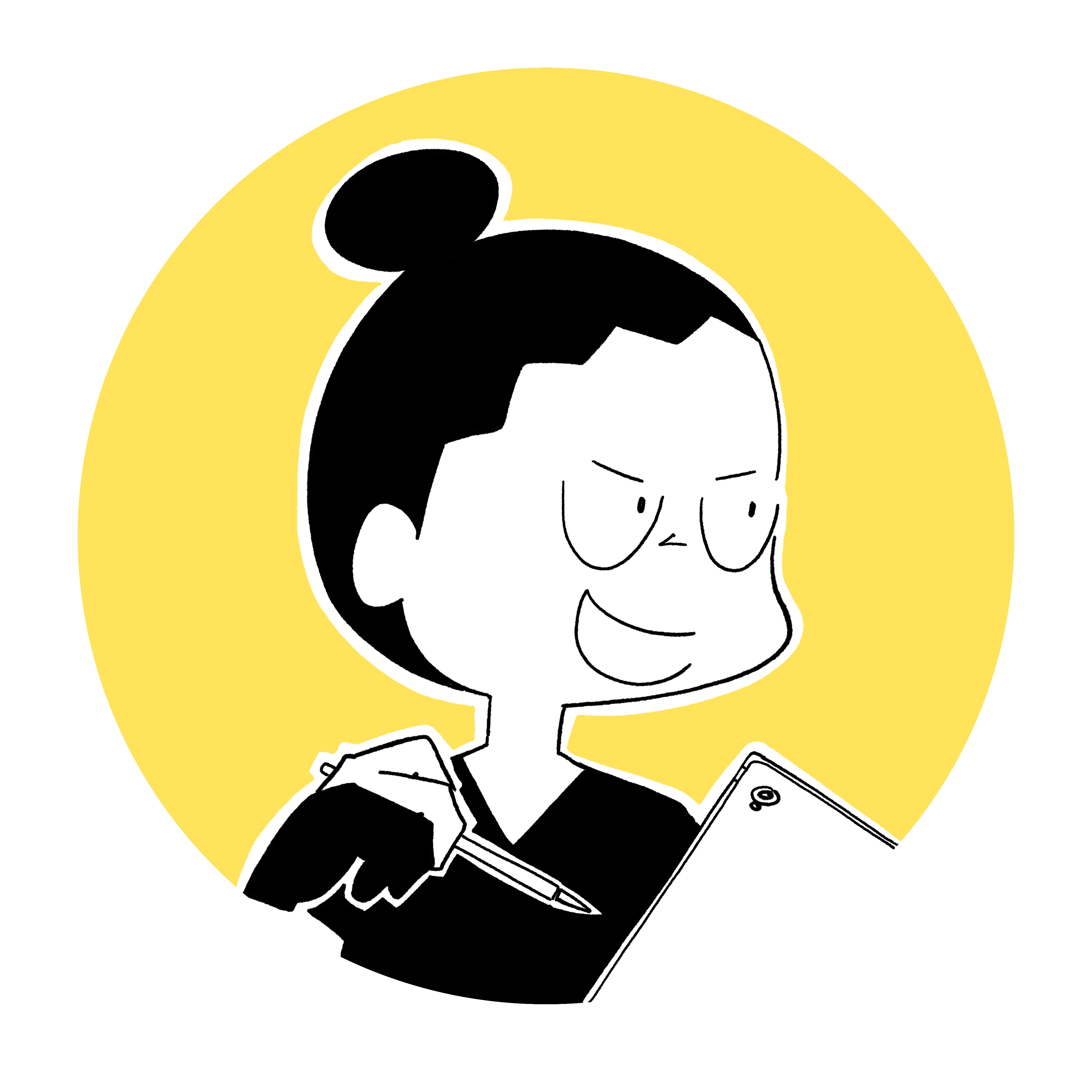

コメントを残す