[ad#ad-1]
[ad#ad-1]

去る者と残る者がいる。
ボランティアといっても、みんなが僕みたいなフリーターで時間に融通のきくわけではない。
学生もいれば、明日から仕事だという社会人もいる。
青葉市子のライブを見終わったあと、僕はバスに乗って帰るヤツらを見送りに明岳寮前まで持って来ていた。
見送りに来ている人間の数は決して多くはなかった。
なかにはシフトが終わった後にそのまま遊びに行ってしまったヤツもいるんだろう。人には人の楽しみ方があるさ。
負担は僕自身が自分の楽しさを優先してしまうような人間なので、今回はみんなを見送りに行こうという気持ちになったのだ。
それに、見送りがあるかないかで言ったら、僕はあった方がいいと思っている。
出発が誰にも気づかれないなんて寂しいからね。
明岳寮前では私服に着替えたボランティアスタッフのみんなが楽しそうに喋っていた。
彼らの体からはまだフジロックの楽しさのエッセンスが抜けていないように思える。それも当然だろう。だって僕たちはまだ苗場にいるのだから。
見送り側の僕としては、誰かに話しかけるでもなく、ただぼおっと彼が楽しそうにしているのを眺めているだけだった。
というか、そこにいるメンバーのほとんどは日中に活動していたメンバーなのだ。シフト時間が昼夜逆転しているせいで、80人以上もいるスタッフたちの中では知らない顔の方が多いくらいだ。
そういう風に手持ち無沙汰な時間を過ごしていると「やっぱり見送りなんて来ない方が良かったのかも」と思わなくもなかった。
仕方がないので僕はちびちびと酒を飲んでいた。
もうこうなったら自分が楽しくなるまで酔っぱらうしかないのだ。
下戸のいいところは少量のアルコールで楽しい気分になれてしまうところだ。
バスに乗り込むメンバーたちが駐車場へ移動するころには、僕はすっかり出来上がっていた。
時間もその頃になると、他の見送りのヤツらがぼちぼちと現れ始める。
結局からむのはいつものメンバーになってしまう。いつものメンバーというのはナイト班のメンバーたちのことだ。これから帰る者も、残る者も関係なしに、くだらない話で盛り上がった。
えだは僕が描いた似顔絵を大事そうに抱えていた。
「これ、荷物に押しつぶされて割れないようにずっと手で持っとくわ!」
というえだはなんだかかわいらしかった。
徹夜明けでいいパフォーマンスが発揮できた似顔絵では決してなかったが、こういう風に喜んでもらえるのが一番だ。まぁ、『描き直したい..』って思うのはいつものことなんだけどね。
帰る予定のスタッフたちが整列してコンクリートの地面の上にしゃがんでいる。
軽トラックの荷台にコアスタッフたちが立って落し物のアナウンスをしている。落し物は例年のごとく雨具などの衣類が多かった。持ち主が見つかる物もあれば、そうでないものもある。
僕は思うの誰けれど、どうして落し物の持ち主は現れないんだろう?ふつう、自分の物が失くなったら気づくと思うのだけれど?そうい人たち(気づかない側の人間)はきっと物を持ちすぎているんだろうね。
一通りアナウンスが終わると、スタッフたちはバスがやってくる場所へと移動することとなった。
長い二列になって歩いていると、僕はいつも遠足を思い出す。
先生に引率されて、どこが目的地なのかわからないまま歩を進める時のぐだぐだした感じは、喋る相手さえいれば苦じゃない。
「ねえ、私の名前覚えてる?」
そう喋りかけてきたのはコアスタッフ(iPledge運営側のスタッフ)のちぇりだった。
今年僕はごみ箱のペイントに事前から関わっていたため、コアスタッフとも顔を合わせているのだが、僕は人の顔を覚えるのが苦手で学生スタッフたちの顔や名前がどうしても思い出せなかった。
というか、彼ら(彼女たち)にとって、僕という人間は
「漫画家志望のフラフラしてる反面教師的人間」
なのだろうけれど、
僕からしてみたら学生スタッフの子たちなんて「コアスタッフ」というくくりでしか認識することができない。
顔を合わせる機会も多くなければ、喋ることだってあまりない。
ただ、彼女の場合、僕に話しかけてくる時の一声が「私の名前覚えてる?」だったから、顔と名前は比較的覚えやすかった。
「えっとーーーー、”チェリ”か”チュリ”でしょ?」
「ちぇりだよ!」
僕の中では「チェリオ」的な音で記憶していたのだ。
「ねえねえ聞いて!」
「なに?」
「Dっているでしょ?」
「あぁ、アイツね」
「Dと一緒に活動することがあったんだけどさーー..」
Dというのは、今回ボランティアスタッフでも参加したヒッピーみたいなヤツだった。
シフトはデイ(日中)だったため、僕と彼が一緒に活動することはなかったが、どうやら彼もフジロックのボランティアを存分に楽しんでいるらしかった。
「Dにね、私、いわれたの」
「なんて?」
「『君に会えてよかった』って!
これって告白だよね!きゃ〜〜〜!私どうしよ〜〜〜!」
僕は思わず笑ってしまった。
なんでかっていうと、Dはそんなキザなセリフを言うようなヤツには全然見えなかったからだ。
もし、僕がそのセリフを言うのであれば、その女のコとよっぽど大変な環境をくぐり抜けたか、もしくは何かしらの活動を、
そうだな青年海外協力隊でマラウィだかで数年一緒に仕事をするような状況にいないと、
僕はそのセリフを口にすることはできないような気がする。
それだけ重みのある言葉だと僕には思えるのだ。
フジッロックのボランティアスタッフでそのセリフを口にできるだなんて、よっぽど日中の活動は過酷を極めたようだ。
僕はニヤニヤしながら、ちぇりの話に耳を傾けていた。
彼女は僕が酔っ払っているものだと思っているからいくらか口が軽くなっているのだ。
僕もここぞとばかりに、大声でシャウトしていた。だって、こういう場面じゃないと歌えないもの。最近大声だしてないもんな。
だいたいこう言う時に僕が歌うのはELLE GARDENの”Make A Wish”なのだ。
そんなふうにして大声で歌っているとなんだかフジロックが終わった後の方が楽しいような気がした。
もうシフトなんて気にしなくていいし、解放された気分だった。誰かと話して歌っているだけで楽しかった。
僕はお酒で記憶が飛んだりすることはない。どんなにヘラヘラしていたって、自分が何をしたか、どんなことを喋ったかははっきしと覚えている。ただ、酔っぱらうと機嫌がよくなってついついくだらないことばかりペラペラ話してしまうことが多い。
まぁ、そんなもんだよね。酔っ払いってさ。

バスが来ることになっていたのは川を挟んだホテルの合い向かいだった。
コアスタッフたちがこれから東京に戻る人たちを整列させていたので、僕は混ざらないように列から離れた。
僕を含め見送りに来たヤツらは気楽だった。地べたに座り込み、ぺちゃくちゃとくっちゃべっているだけでよかった。高校の生活指導担当の先生とかが見たら何か言われそうなダラけ具合だった。
何度も書くようだが、活動はついさっき終わったのだ。
責任を持って(そして楽しんで)会場のごみ資源の分別ナビゲートに精を出していた。そこに僕たちがいるかいないかではごみの分別度合いは大きく異なるだろう。
そして僕たちは間違いなく会場のピースキーパーの役割も担っていた。
フジロックという会場の雰囲気作りの一旦を担ってたの僕たちだった。
だから祭りが終わった後は、そんなふうにリラックスしていたってバチも当たらないさ。
ここに残る者は明日は仕事があるけど、あとは各々の裁量に任せて酒を飲んだり、夜更かしすればいい。
ここに残る人間は翌日の「バイト日」というものに参加することになっている。
来場者たちが帰った後の会場の、自分たちが関わったごみ資源の分別周りの片付けや撤収を行うのだ。
そう書くと大変な肉体労働のように聞こえるかもしれないが、関係者しかいない苗場もまた乙なものなのだ。だって、なかなかないよね。フェスの後の会場に残れるなんてさ。
それにバイト日にも楽しいところはある。4日間行動を共にしたスタッフたちと一緒に仕事をするのはやはり楽しい。やるべきことはあるが、誰かに急かされて動く必要もないし、お金がもらえるのであればなおさら嬉しい♪

バスは30分ほど遅れてやってきた。
僕たちは先に帰っていく仲間たちを見送ると、再び、祭りの余韻の中へ戻っていった。
「きっとこの後も長い夜が続くに違いない!」
僕はそう考えていたが、フジロック最終日の終わりは意外とあっけないものだった。
明岳寮前の飲食エリアで適当に腹を満たすと、あとは手持ち無沙汰になってしまった。
楽しさの流れのようなものが途切れてしまったような感じさえした。さっきまであんなに楽しい気分だったのに、なぜだか、今はお酒を飲んでも何か食べてもいまいちピンと来ない。
楽しさにも「流れ(ノリ)」のようなものがあるのかもしれない。楽しいと感じた時は一気に楽しまなくちゃだめなのだ。きっと。
楽しさのエネルギーはバスを見送りに行った時に、苗場の夜の空気感の中に散っていってしまったのかもしれない。
僕はナイト班の他のメンバーと一緒になってしばらくパレス・オブ・ワンダーをウロウロしていたけれど、だんだん自分が何をやっているのかわからなくなってきてしまった。
連日の疲れもあったか、体はこれ以上のアルコールも食べ物もなにも求めてはいなかった。
とびーと一緒に仲良くラーメンすすりながら、球体の中を駆け巡るバイクパフォーマスをひとしきり眺めると、僕は今日という一日を切りあげることにした。
どうしてだろ?去年はもっと楽しかったのに。
あぁ、そうか。
あの時一緒に遊んだヤツらが今ここにいないからだな..。
いやさ、去年はすごかったんだよ。
メリーゴーランドみたいな回転ブランコがあってさ、誰かが曲芸的な乗りかたをしたり、泥酔したヤツがいたり、出店のブースの裏で吐いたりするヤツがいたり、そのまま背負われて宿舎に戻るヤツなんかがいてさ。
なんだかずっと笑ってた気がするな。
まぁ、例年がいつもそうとは限らないってことかぁ..。
それでも時刻は2時を回っていた。

部屋に戻ると僕一人しかいなかった。
同室で残っているのはどうやらTだけのようだ。他の二人の荷物は片付けられ、シーツや布団もそこにはなかった。
シャワーを浴びて歯を磨くと、僕はモソモソと布団の上に横になった。
[ad#ad-1]
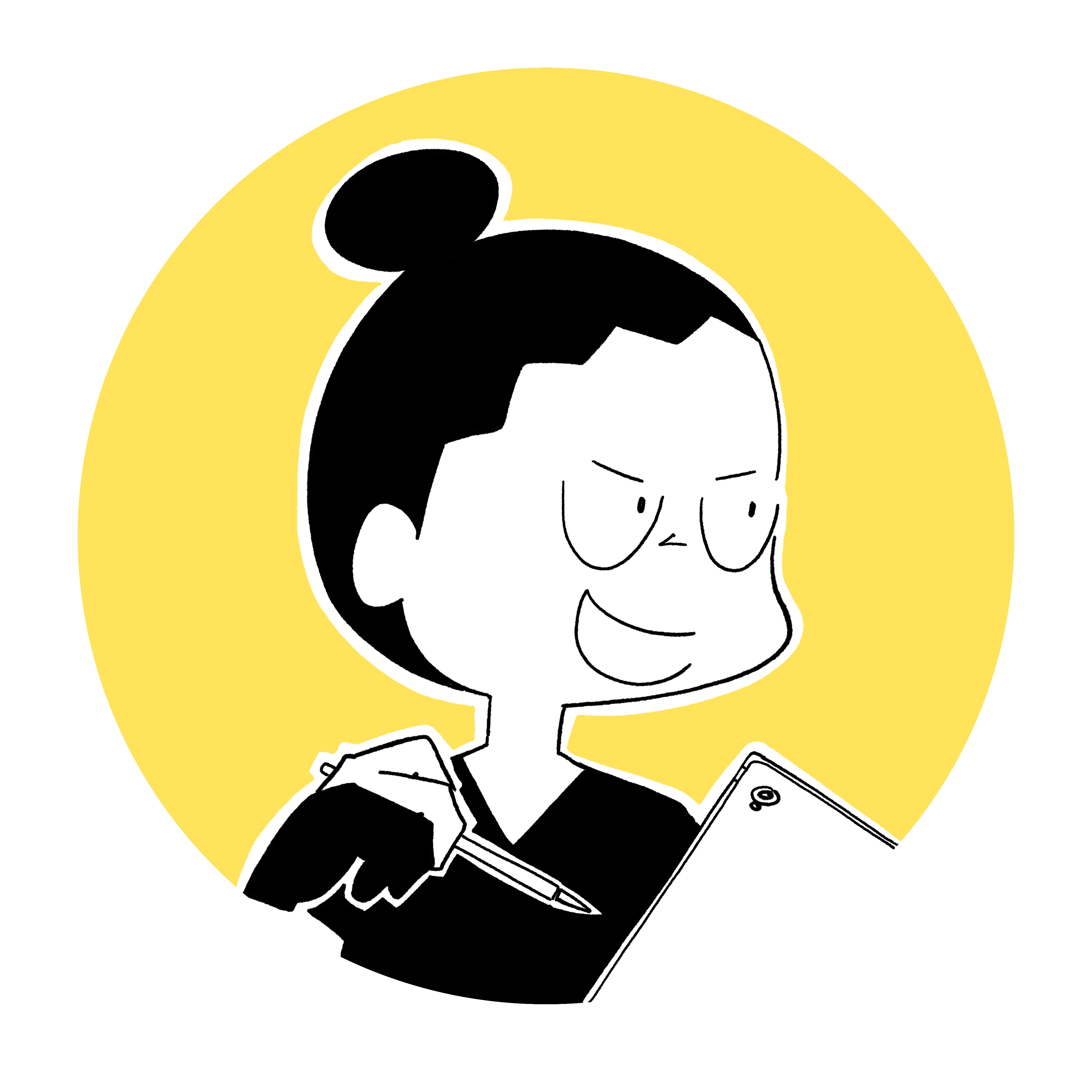

コメントを残す