[ad#ad-1]

フジロックが終わって早くも一週間以上が経ってしまった。
今思うと、あの数日間はずっと前に起こったことのような気がするし、
濃密な数日間だったので、あの時感じたフィーリングは今も自分の中にまだ残っている。僕の気持ちの何パーセントかは苗場に留まったままなのかもしれない。
そんな風にフジロックから帰ってきた人が陥るであろう一種の軽い鬱状態を
フジロスという。
さあ、旅する漫画家の僕は一体どんなフジロックを過ごしてきたんだろうね。
また、グダグダ書くからさ、どこかの誰かの暇つぶしにでもなればいいと思う。
なんだか書き出したら止まらなくなっちゃって、まぁ例のごとく、長いだけの大したことない日記なんだけどさ。記憶をとどめておくためにもいいかもしれないな。
っていうか、どういう風にフジロックをまとめていいのかさっぱりわからないから、とりあえず思ったことだけ書くよ。
さぁて、はじまりはじまり〜〜♪
今回のフジロックは何がなんでも行きたいと思った。
というのは、今回のヘッドライナーが僕のどストライクだったからだ。
ゴリラズなんて高校生から聴いてきたバンドだし、帰国してからはビョークに一時期ハマったし、作業音楽でエイフェックスツインにお世話になったことだってある。
グリンステージのトリを務めるであろうアーティストを見るだけでも、僕はフジロックに行きたくてたまらなかった。
そして僕のフジロックに対する関わり方は大学生の時から一貫して同じスタイルを貫いて要る。
アイプレッジのボランティアとしてフジロックに参戦するのだ。
アイプレッジ(旧ごみゼロナビゲーション)は環境対策NGOで、大学生の時に一時期スタッフとして関わっていたことがある。そこを出てからもなんらかの形で関わってきた。考えてみれば継続的な付き合いではないにせよ、7年以上もアイプレッジとの付き合いがあるのだ。
ところで、なんで「参戦」っていうんだろうね。なんかかっこいいけどね。モッシュやダイブがあるような激しいライブだったらまだしも、野外音楽フェスだからね。どっちかっていうと、ピースな雰囲気の方が優っているきがするけどさ。
でも、苗場の天気は変わりやすいからさ。悪天候にもめげずにフジロックを楽しむって意味では「戦い」なのかもしれないな。まぁいいや。
僕はボランティアとして参加したいがために、積極的にアイプレッジにアプローチをかけるようになった。フジロックに設置するごみ箱のペイントがそれだ。
一度は描かないつもりだったが、やっぱり一年だけじゃもったいない。無名に等しい僕の今のレベルでは自分の宣伝にはならないにせよ、自分の作品を会場に置いてもらえるだけでも意味があると思った。僕より上手いアーティストでも、人によってはノーギャラで描きたいという人もいたと思う。これはある意味では僕にとってのチャンスでもあったのだ。
そうして、2泊3日で倉庫に泊り込みをして作品を仕上げた上でアイプレッジの募集するボランティアに応募した。
ボランティアの人数には制限がある。希望者が全員アイプレッジのボランティアスタッフとして会場にいくことはできないのだ。
それでも、ボランティアスタッフとして今年もアイプレッジに迎えられたことには感謝したい。僕のささやかな(ある意味タフな)献身が認められたのかもしれない。

ボランティアコースは前夜祭からフジロック後のバイト日も含めた5日間のコースだ。
幸いバイト先が理解のあるところなので、事前から申請することによって、僕はフジロックを楽しむスケジュールを組むことができたのだ。
これが飲食店でバイトしていたのであれば叶わなかっただろう。っていうか、2012年のバイト時代は実際そうだったもん。「あのぅ..、店長、フジロックに行くために5日間休みたいんですけど..」「は?お前なにバカなこと言ってんの?」ってそんな感じ。
今の環境は対外活動をする上で恵まれていると思う。
社長、こんなフラフラしているヤツを雇ってくれてありがとうございます。
いつもは
バタバタするパッキングも前日のお昼過ぎからはじめ、買い出し備品もしっかり準備して望んだ。
出発前日に床についたのは夜の1時。
笑っちゃう話なんだけど、ワクワクしすぎてその日は寝られなかった。
荷物が多い状態で満員電車に乗りたくなかったので、僕は始発に乗ってボランティアスタッフの集合場所である新宿駅まで向かった。
まさかフジロックにディジュリドゥを持っていったのは自分でも笑えた。でも、あの楽器の持つ不思議なパワーをどこか信じてみたい気がしたのだ。「フジに持っていけば何かが起こる!」そう僕は信じていた。

家を出てすぐのコンビニに立ち寄った時、いつものおじちゃんが僕の格好を見て「釣りにでも行くの?」と驚いた顔で訪ねてきた。きっとケースに入ったディジュリドゥを釣竿かなんかだと勘違いしていたのだろう。
「フジロックに行くんです」と答えると、おじちゃんは「私も行ってみたかったけれどね。大変なんでしょ?暑かったり、雨が降ったり」と言った。
一般的なフジロックのイメージというものはどういうものなのだろうな。きっと。
朝の涼しげな空気の中、最寄り駅まで15分をかけて歩き、すでにホームで待っていた始発の電車に乗り込んだ。バックパックを背負って歩いた体はいくらか汗で火照っており、電車の中を快適な温度に冷やしてくれる空調には感謝せざるえなかった。
電車が走り出すと、僕はずっと外の景色を眺めていた。
バックパックと共に移動をすると、僕が感じるのはやはり「自分が旅をしている」という感覚だ。それは旅から帰ってきても僕の中に残っている。この感覚が消えることは一生ないだろう。忘れたくない感覚だ。

新宿まで行くのに、品川駅で乗り換えた。
半袖シャツのサラリーマンの群れが、何か魚の群れのように思えた。
その時の僕の格好と言ったら、ジーンズにTシャツ、バックパック。片手にはディジュリドゥといった格好だった。木曜の通勤時間にそんな格好をしている僕は反社会的だなと思わなくもない。

新宿駅西口に出ると、ちょうど今回フジロックに設置するごみ箱のペイントをした一人であるデイミーとばったり出くわした。

同じようなラフな格好をして、バックパックを背負ったやつを見ると、どこか安心する。
喫煙所で眉間にしわを寄せるサラリーマンに混じりながら、巻きタバコを吸う。こういう時間も考えようによってはとても贅沢なんだなと僕は思う。早朝の新宿駅西口前の喫煙所でくだらない話で笑い合い、タバコを吸い終わると、僕とデイミーはコンビニへ行きコーヒーを買って、集合までの時間をゆっくりと過ごした。
話した内容と言えば食にまつわることばかりだった。
自由大学の大学4年生である彼は、現在ベジタリアン生活の真っ只中らしい。
「それじゃフジロックで何を食べるの?」と僕が尋ねると、「いや〜〜〜..だから困ってるんですよね」とデイミーは言った。フジロックには数多くの飲食出店がある。彼の心がおれるのも時間の問題だろうなと僕は思った。でも、ひょっとしたら、ベジタリアン向けの出店もあるかもしれないな。ある意味ではベジタリアンがフジロックをどのように過ごすのか、いい実験になりそうだ。まぁ、僕はやらないけどね。
僕の食事情と言うと、最近ではめっぽう食が細くなり食べなくても平気な体になってしまっていた。
朝食はヨーグルトと野菜ジュース。昼はナッツとか。体にはよくないとはわかっていても菓子パンを一個食べることも。そして夜は食べると眠くなって絵が書けないので食べない(笑)。食べたとしてもキムチをちょっととか。2日だか3日に一度は外食をして足りない分?をカバーするという超偏食的な食生活だ。まぁ、今の所、それで問題はないので、こっちもしばらくは人体実験をしてみようと考えて要る。
でも、フジロックは例外だ!
なんていたって一年に一回しかないフジロックに僕は行くのだ。
その意味では出店も一年に一回だけ。そんな場所で食事を楽しまないでどうするのだ!
「フジロックでは思う存分食べてやるぞ!」という意気込みが僕の中にはあったのだ。

工学院前で集合するメンツの半分くらいは去年も見たことのある顔ばかりだった。
あの時初めて会ったヤツらは、去年のフジロックを終えた後には「馴染みのあるヤツ」に変わっていた。
僕は引きこもりがちの生活をしているので、フジロックが終わって日常生活に戻った後も、彼らとしょっちゅう顔を合わせていたわけではないが、
一年ぶりに顔を合わせても久しぶりだという感じはしなかった。そういう感覚になるのはきっとSNSで誰かと繋がっているからだろうな。
工学院前でそのように知り合いと会う時間は、なんだか遠足前の小学生たちの集まりにでも見えなくはなかった。
だけど、僕たちはボランティアスタッフとして苗場へ行くのだ。
多くの人がイメージするであろう無償での労働だとかそいう意味合いのボランティアをするつもりは僕たちには毛頭ない。
僕たちはフジロックに文字通り遊びに行くのだ。
ただ、遊びの種類が違うだけだ。環境対策NGOアイプレッジのボランティアスタッフとして遊ぶのだ。
ワクワクしながらバスに乗り込む。
ディジュリドゥは割れると怖いので車内に持ち込んだ。みなそれぞれが席につき、興奮冷めやらぬまま、ぺちゃくちゃとおしゃべりをしている。そんな中9時を過ぎるとバスはゆっくりと工学院前を出発した。

バスが出発してもしばらくは眠ることができなかった。
苗場まで行く道のりを、眠ることによって見逃してしまうのは、なんだかとても勿体無いような気がするのだ。
考えてみれば僕は昨日から一睡もしていない。24時間まるまると起きていることになるが。眠気は感じない。
『ここで眠っておかなければ今日の前夜祭から始まる活動に支障をきたすぞ』と、なんとか眠りにつこうとするが、気持ちはやっぱり落ち着かないままだ。
こっそり持ち込んだブランデーの小瓶をこっそりとチビチビ飲むことによって、僕はようやく眠りにつくことができた。
気づいた時には苗場スキー場へと続く山道をバスが登って要る最中だった。
[ad#ad-1]
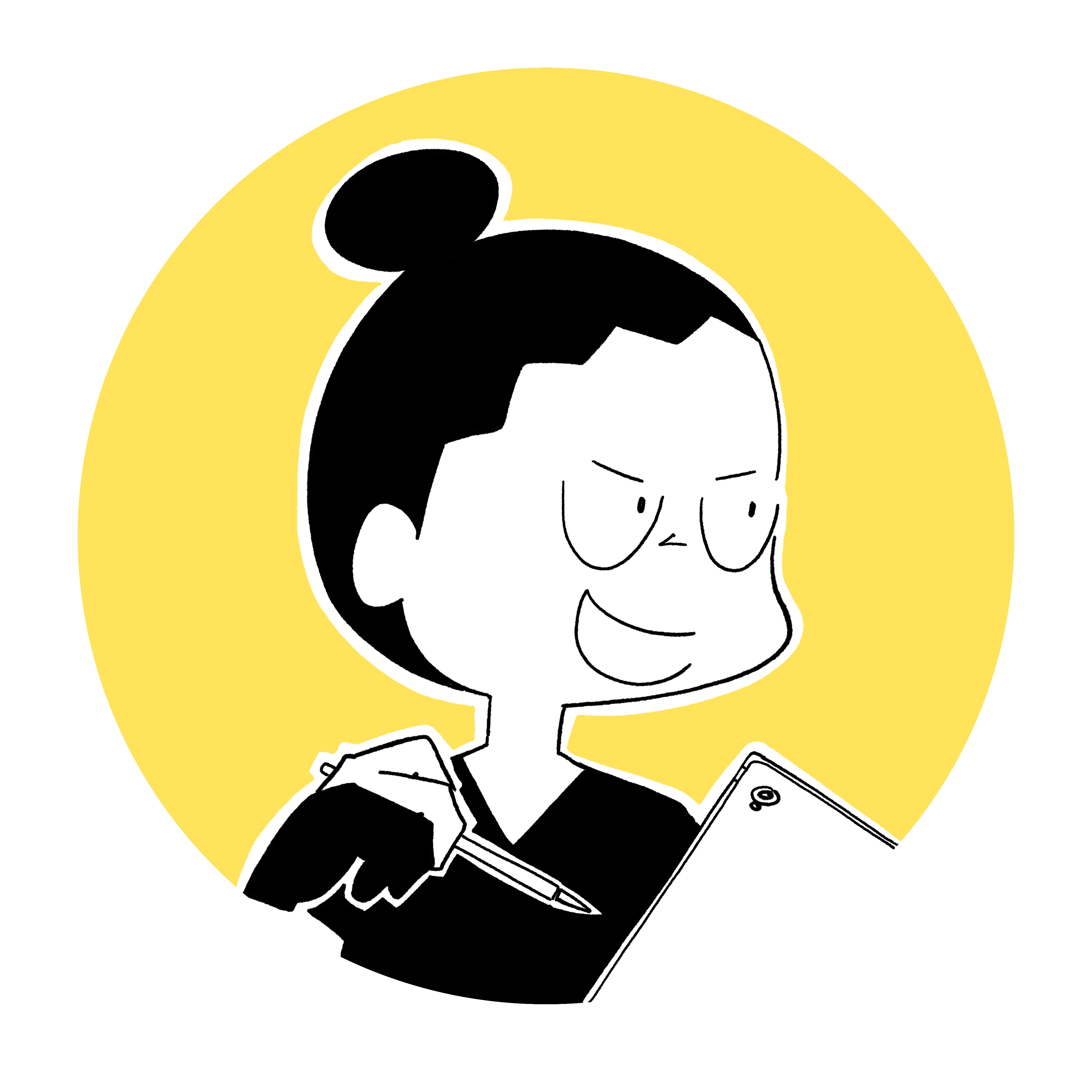

コメントを残す